糖尿病にいい食べ物とは?血糖値を下げる食事のコツとおすすめ食品のランキングを紹介
2型糖尿病の治療において、食事の見直しは欠かせない要素のひとつです。
2型糖尿病の治療に適した食べ物とは、単に糖質が少ない食材ということではありません。
肥満の解消に効果的であり、血糖値の急上昇を抑え、体の代謝を改善するのに役立つような特徴を持つ食品を指します。
この記事では、食事を含む生活習慣と深く関係する2型糖尿病を対象に、病状の進行を防ぎ、血糖値の管理に役立つ食べ物の具体例、食事や生活習慣のポイントについて詳しく解説します。
さらに、糖尿病の方でも安心して楽しめるレシピも紹介していますので、日々の食事の工夫にお役立てください。
糖尿病とは
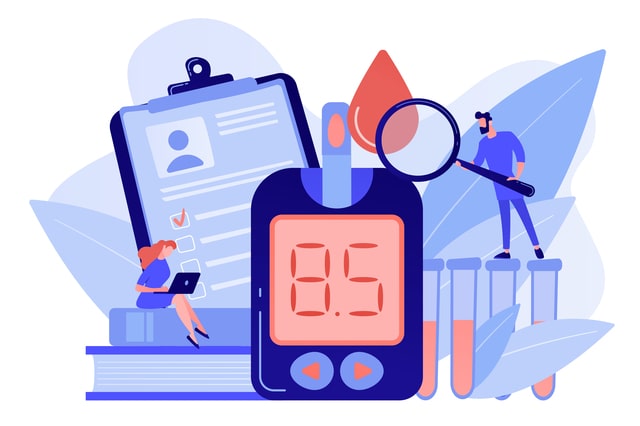
糖尿病とは、血糖値を調整するホルモンであるインスリンの作用が不足することで、血糖値が慢性的に高くなる病気です。
1型と2型で原因が異なり、治療方法も異なります。
この記事では、主に2型糖尿病について解説します。
糖尿病の種類
糖尿病には大きく分けて 1型糖尿病 と 2型糖尿病 の2種類があり、それぞれ原因や治療方法が異なります。
自己免疫の異常などによって、膵臓のβ細胞が破壊され、インスリンがほとんど分泌されなくなる病気です。
発症年齢は若年層に多い傾向があり、インスリン注射が不可欠です。
食生活や運動不足、遺伝的要因などが関係し、インスリンの分泌量が不足したり、働きが低下したりすることで発症します。
主に中高年に多く見られ、食事療法や運動療法、必要に応じて薬物療法が行われます。
2型糖尿病の診断基準と症状
2型糖尿病の診断は、血液検査の数値だけでなく、症状の有無、家族歴、体重の変化などを総合的に判断して行われます。
■糖尿病の診断基準(高血糖の基準値)
以下のいずれかの数値が基準を超えると、糖尿病が疑われます。
- 空腹時血糖値:126 mg/dL 以上
- 75g経口ブドウ糖負荷試験(OGTT)2時間値:200 mg/dL 以上
- HbA1c(ヘモグロビンA1c):6.5% 以上
また、2型糖尿病は、初期では自覚症状がないことも多くなっています。
一方、2型糖尿病による高血糖が続くと、以下のような症状が現れることがあります。
- 口渇(のどの渇き)
- 多飲(水分を多く摂る)
- 多尿(尿の回数・量が増える)
- 体重減少(食事量が変わらないのに痩せる)
また、2型糖尿病により合併症を引き起こすと、その症状が現れることがあります。
- 網膜症…視力低下や失明のリスク
- 腎症…腎機能の低下、最悪の場合透析が必要
- 神経障害…しびれ、痛み、感覚異常
- 動脈硬化性疾患…血管が狭くなり、血流が悪化することで発症
2型糖尿病を放置すると、高血糖が続くことで血管がダメージを受け、さまざまな合併症や動脈硬化性疾患を引き起こすリスクが高まります。
- 動脈硬化(血管が硬くなり、血流が滞る)
- 心筋梗塞(心臓の血流が途絶え、心筋が壊死する)
- 脳卒中(脳の血管が詰まり、脳細胞が損傷する)
糖尿病は進行するまで自覚症状が少ないことが多いため、早期からの血糖管理が重要です。
2型糖尿病の原因と治療
2型糖尿病は、生活習慣や遺伝的要因が複雑に関係して発症します。
特に以下の要素がリスクを高めることが知られています。
- 遺伝的要因…家族に糖尿病の人がいると発症リスクが高まる
- 肥満…特に内臓脂肪の増加はインスリンの効きを低下させる
- 食生活の乱れ…過食、高糖質・高脂肪食の摂取
- 運動不足…エネルギー消費の低下やインスリン抵抗性の悪化
糖尿病治療では、血糖値をできるだけ正常範囲に保ち、合併症を予防することが重要です。
また、血糖コントロールに加えて、以下の健康指標も適正範囲に維持することが求められます。
- 体重…肥満の解消
- 血圧…高血圧の予防・改善
- 血中脂質…脂質異常症の予防
糖尿病の治療には、食事療法・運動療法・薬物療法の3つがあります。
治療内容は病状や進行度によって異なりますが、どの段階でも生活習慣の改善が治療の基本となります。
- 食事療法…食事内容の見直し
- 運動療法…運動不足の解消
- 体重管理…肥満の解消
糖尿病は進行するとさまざまな合併症を引き起こすため、早期から適切な生活習慣の改善が重要です。
2型糖尿病の食事療法とは

糖尿病の改善には、食事療法が最も重要な取り組みのひとつです。
適切な食事管理を行うことで、体重減少、HbA1cの低下、血中脂質や血圧の改善効果が期待され、糖尿病に関連する代謝の改善につながることが知られています。
食生活を整えることで、血糖値の安定だけでなく、合併症のリスク低減にも役立つため、継続的に取り組むことが大切です。
摂取カロリーとPFCバランスの管理
糖尿病の改善には、摂取カロリーとPFCバランスを適正範囲に保つことが重要です。
肥満は糖尿病のリスク要因のひとつであり、適正体重を目指すことで血糖値の改善が期待できます。
また、脂質異常症や高血圧を伴う場合には、適正なカロリー管理によってこれらの数値の改善にもつながります。
肥満の解消には、目標体重に応じた適切なカロリー摂取が必要です。
一般的に、65歳未満の方ではBMI22に相当する体重が目安となりますが、適正な目標体重や摂取カロリーは、現在の体重、年齢、病態、身体活動量によって異なります。
そのため、医師や管理栄養士に相談しながら、自分に合った数値を設定することが大切です。
1~2kg程度の減量であっても、血糖値や血圧、脂質の改善に効果があることが報告されています。
そのため、短期間での急激な減量を目指すのではなく、 腹八分目を意識しながら、カロリーを抑えた食材選びを心掛けることがポイントです。
また、糖尿病の食事管理では、特定の栄養素だけに偏るのではなく、PFCバランス(たんぱく質、脂質、炭水化物のバランス)の良い食事を心がけることも重要です。
■推奨される栄養素バランス(日本糖尿病学会(2013年)の食事療法の提言)
- 炭水化物 …総摂取カロリーの 50~60%
- たんぱく質 … 摂取カロリーの20%以下
- 脂質 …炭水化物・たんぱく質の残り( 20~30%程度 )
- 食物繊維 … 1日20g以上
これは、健康な人の理想的な栄養バランスとほぼ同じ であり、特別な制限を設ける必要はありません。ただし、糖質や脂質の種類に注意しながら、適切に摂取することが求められます。
具体的な食事の構成として、主食・主菜・副菜をそろえることが大切です。
- 主食 …ごはん、パン、麺類など
- 主菜 …肉、魚、卵、大豆製品などのおかず
- 副菜 …野菜、海藻、きのこ類を使ったおかず
毎食この3種類を揃えることで、栄養バランスを自然と整えやすくなります。また、食物繊維を積極的に取り入れることで、血糖値の急上昇を防ぎ、糖尿病の管理にも役立ちます。
糖質は摂取源を選ぶ
糖尿病だからといって糖質(炭水化物)を完全に避ける必要はなく、むしろ適量を適切な食品から摂取することが重要です。
2013年の「日本糖尿病学会の食事療法に関する提言」によると、糖尿病の方も血糖値が正常な人とほぼ同じく、食事全体のカロリーの50~60%を炭水化物から摂取することが推奨されています。
しかし、糖質の摂取源によって血糖値や健康への影響が異なるため、どのような食品から糖質を摂るかを意識することが大切です。
避けたい糖質の摂取源として、糖類が挙げられます。
砂糖(ショ糖)の摂取量が多いと、血中コレステロールや中性脂肪の増加、血圧の上昇、2型糖尿病の発症リスクを高めることが報告されています。
■糖質摂取のポイント
- 砂糖を多く含む食品(菓子類、ジュース類)を控える
- 果糖を含む飲み物(清涼飲料水、加糖のスポーツドリンク)を控える
- 調味料(砂糖、みりん、ハチミツなど)を控える
- 低カロリー甘味料を活用する
一方で、必要な糖質は摂取する必要があるため、適度な摂取を心がけましょう。
- 主食(ごはん、パン、麺)は毎食適量をとる…主食抜きや主食ばかりの偏った食事は避ける
- 果物は適量(1日100g程度)を守る…過剰摂取を避け、生の果物をとる
なお、具体的な摂取量や食事内容は個々の健康状態によって異なるため、医師や管理栄養士と相談しながら決めることをおすすめします。
食物繊維を意識する
食物繊維の十分な摂取は、HbA1cの低下や糖尿病に関連する心血管疾患のリスク低下に役立つことが知られており、積極的に摂ることが推奨されています。
食物繊維は野菜、海藻、きのこ類、精製度の低い穀類に豊富に含まれています。
普段の食事で以下のような工夫を取り入れると、無理なく摂取量を増やすことができます。
- 白米を玄米、雑穀米、麦飯などに置き換える
- 小麦製品は全粒粉入りのものを選ぶ
- 野菜、海藻、きのこ類を意識的に取り入れる
- 具だくさんのスープや味噌汁にすることで手軽に食物繊維を増やす
食物繊維の目標摂取量は1日あたり20g以上とされていますが、日本人の平均摂取量は17~19g程度とわずかに不足しているのが現状です。
不足している1~3gを補うためには、1日1回、食事に食物繊維が豊富な食品をプラスすることを意識しましょう。
例えば、野菜を使った副菜を1品追加する、海藻やきのこを活用した料理を取り入れるといった工夫が有効です。
たんぱく質は適量を
糖尿病の食事療法ではたんぱく質不足を避けつつ、過剰摂取にも注意することが大切です。
糖質を控えることに意識が向くあまり、たんぱく質を摂りすぎてしまうケースもあるため、適量を意識した食事を心がけましょう。
日本糖尿病学会の食事療法に関する提言と日本人の食事摂取基準2020年版をもとにすると、たんぱく質の適正な摂取量は総摂取カロリーの15~20%程度とされています。
これを超えて過剰に摂取すると、動脈硬化性疾患などのリスクを高める可能性があるため注意が必要です。
適正なたんぱく質の摂取ポイントとしては、主菜(肉、魚、卵、大豆製品)を毎食適量とることが挙げられます。とはいえ、主菜ばかりに偏らず、副菜(野菜・海藻・きのこ類)をバランスよく取り入れることも大切です。
1回の食事で適切なたんぱく質を摂るためには、「手のひら1枚分」の量を目安にするのがおすすめです。これは肉・魚・卵・大豆製品など、主菜として取り入れる食材の適正量を示す目安となります。
ただし、病状や体質、体格、生活習慣によって適切な摂取量は異なるため、具体的な調整が必要な場合は医師や管理栄養士に相談するのが安心です。
脂質は量と質に注意
脂質は1gあたり9kcalとカロリーが高いため、過剰摂取は肥満につながります。
しかし、糖尿病の改善においては脂質を極端に制限する必要はなく、適量を維持することが重要とされています。
糖尿病における脂質摂取の適正バランスは、2013年の「日本糖尿病学会の食事療法に関する提言」によると、脂質の摂取割合は総カロリーの20~30%が適切とされています。
特に、脂質が25%以上になる場合は、その質(種類)にも注意を払うことが推奨されています。
肉類(特に脂身)や乳製品に多く含まれる飽和脂肪酸は、糖尿病や動脈硬化のリスクを高めるため、摂取を控えめにしましょう。
一方、魚の油や植物油に多く含まれる不飽和脂肪酸は、HbA1cの低下や糖尿病リスクの軽減に役立つことが報告されています。
■脂質の質を改善するためのポイント
- 油脂の摂取量を適量に抑える…揚げ物を減らし、焼く・蒸す・茹でるといった調理法を活用する、乳製品は低脂肪・無脂肪のものを選ぶ
- 飽和脂肪酸を減らし、不飽和脂肪酸を増やす…バターやラードではなく、オリーブオイルやキャノーラ油などの植物油を活用する、肉の脂身を減らし、魚を積極的に取り入れる
適切な脂質を適量とることで、血糖値の安定や生活習慣病予防にもつながるため、日々の食事の中で意識して取り入れていきましょう。
アルコールは控えめに
アルコールの過剰摂取は、摂取カロリーの増加や栄養バランスの乱れ、低血糖のリスクを引き起こす可能性があります。
これにより、血糖値の管理が難しくなり、糖尿病のコントロールにも悪影響を及ぼすことが知られています。
とはいえ、糖尿病の治療中であっても、必ずしも完全に禁酒しなければならないわけではありません。しかし、血糖値の安定を考慮し、適量の範囲内で楽しむことが大切です。
日本糖尿病学会の「糖尿病診療ガイドライン2019」では、1日あたりのアルコール摂取量の目安として最大25gまでが推奨されています。市販の酒類には含まれるアルコール量が表示されることも多くなってきましたので、参考にするとよいでしょう。
また、適量を守りつつお酒を楽しむためのコツとして、飲む量を決めておく、度数の高いものは避ける、糖類を多く含むカクテルやリキュール類は控えめにするなどが挙げられます。
ただし、糖尿病以外に高血圧や脂質異常症、肝疾患などの合併症がある場合は、飲酒を控える必要があることもあります。具体的な摂取量については、医師や管理栄養士と相談しながら決めることが安心です。
減塩を心がける
塩分(食塩・ナトリウム)は、摂取量が多くなると高血圧の原因となり、糖尿病に関連する動脈硬化性疾患のリスクを高めることが知られています。
そのため、糖尿病の管理においても、塩分を控えめにすることが推奨されています。
厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2020年版)」によると、1日あたりの食塩摂取目標量は高血圧がない場合で男性7.5g未満、女性6.5g未満となっています。
また、高血圧がある場合には男女ともに6.0g未満となります。
この目標値は、健康な人にも推奨されている基準と同じですが、日本人の平均的な塩分摂取量はこれを大きく上回っているのが現状です。
そのため、高血圧を指摘される前から、意識的に減塩に取り組むことが理想的です。
■塩分を減らすためのポイント
- 出汁や香辛料、酢・柑橘類を活用する…うま味や酸味を活かして減塩
- 汁物の塩分を控える…味噌汁やスープは1日1杯まで
- 加工食品の摂取を減らす…漬物・ハム・ソーセージなどは塩分が多い
- 醤油やドレッシングは「かける」より「つける」…量を調整しやすい
- 減塩調味料を活用する…塩分カットタイプの醤油や味噌を使用
このうち、取り入れやすいものから実践できるとよいでしょう。
糖尿病にいい食べ物ランキング
ここからは、これまで解説した糖尿病の食事のポイントを踏まえ、血糖値の管理や糖尿病の改善に役立つ食材を具体的に紹介します。
いずれも上手に取り入れることで糖尿病の食事療法に役立つ食品です。
ただし、これらの食材を多く摂取すれば血糖値が下がるわけではありません。
重要なのは、食事全体のカロリーや栄養バランスを考えながら取り入れることです。
特定の食品に偏らず、多様な食材を組み合わせながら、無理なく継続できる食生活を心がけましょう。
1位…葉物野菜

葉物野菜は野菜の中でもでんぷん質(糖質)が少なく、よってカロリーが低いことから、食事のボリュームを維持しながら摂取カロリーを抑えるのに役立つ食品です。
さらに、食物繊維の豊富な摂取源でもあり、たっぷり食べることで血糖値の上昇を抑え、腸内環境の改善にもつながります。
■糖質の少ない葉物野菜の例
- 小松菜
- ほうれんそう
- 春菊
- チンゲンサイ
これらの野菜は糖質が少なく、ビタミンやミネラルも豊富に含まれています。
ただし、特定の野菜に偏らず、さまざまな種類の野菜をバランスよく摂取することが大切で、量としては1日あたり350gの野菜を目安に、小鉢1皿(約70g)を5皿程度とれると理想的です。
一方で、レンコンやカボチャのようなでんぷん質を多く含む野菜ばかりを食べると、糖質の摂取量が増えるため注意しましょう。
2位…精製度の低い穀類

一般的な白米や小麦粉などの穀類製品は、「精白」という工程を経て作られています。
一方で、精白せずに穀物を丸ごと使用した穀類(全粒穀物ともいう)は、食物繊維を多く含むため、糖尿病の食事管理に適した食品のひとつとされています。
■全粒穀物の例
-
玄米
-
小麦全粒粉
-
雑穀(ひえ、あわ、キヌア、アマランサスなど)
-
大麦(押し麦、もち麦)
-
ライ麦
-
オートミール(オーツ麦を加工したもの)
白米や小麦粉の一部を全粒穀物に置き換える形で取り入れると、食物繊維を無理なく増やせるためおすすめです。
ただし、精製された穀類と比べて糖質やカロリー自体は大きく変わらないため、摂りすぎには注意が必要です。
3位…きのこ

きのこ類は野菜類と同様、低カロリーで食物繊維が豊富な食材であり、糖尿病の食事管理に役立ちます。
■おすすめのきのこ類
- えのきたけ
- ぶなしめじ
- しいたけ
- エリンギ
これらのきのこを活用することで、食事のボリュームを増やしながらカロリーを抑えることができます。
炒め物やスープに加えたり、冷凍保存して必要なときに使えるようにしておくと便利です。
また、価格が比較的安定しており、生のまま冷凍保存できるため、日常的に取り入れやすいのが魅力です。
4位…海藻

海藻類も野菜・きのこと同様、低カロリーで食物繊維が豊富な食品です。
特に、乾燥品や調味済みの加工品が多く、保存性に優れているため、手軽に取り入れやすいのが特徴です。
■おすすめの海藻類
- わかめ
- めかぶ
- もずく
- ひじき
サラダやスープに加えたり、副菜として活用することで、手軽に栄養バランスを整えることができます。食事全体のカロリーを抑えつつ、食物繊維の摂取量を増やすために、積極的に取り入れましょう。
5位…大豆製品

大豆製品は植物性食品でありながら良質なたんぱく質を豊富に含み、主菜の食材として活用できるのが特徴です。
肉類と置き換えることで、たんぱく質の摂取量を確保しながら飽和脂肪酸の摂取を抑えることができます。
さらに、納豆や蒸し大豆のように大豆そのものを食べる形では食物繊維も摂取できるため、糖尿病の食事管理に適した食品のひとつです。
■大豆製品の例
- 豆腐
- 納豆
- 蒸し大豆
- 大豆ミート(ソイミート)
- 豆乳
大豆製品はその形態によって使い分けができるのが魅力です。
たとえば、豆乳は牛乳の代わりに使うことで飽和脂肪酸の摂取を抑え、大豆ミートは肉のような食感を楽しめるため、肉料理の代替として取り入れやすいのが特徴です。
6位…魚

バランスの取れた食事の食材として魚を積極的に取り入れましょう。
魚に含まれる油には、HbA1cの低下を助ける「多価不飽和脂肪酸」が豊富に含まれています。
一方で、肉類に多く含まれる「飽和脂肪酸」は、糖尿病や動脈硬化のリスクを高める要因となるため、肉の代わりに魚を積極的に取り入れることで、脂質のバランスを改善することができます。
多価不飽和脂肪酸を多く含む魚類には、以下のような「青魚」が挙げられます。
■多価不飽和脂肪酸の多い青魚の例
- イワシ
- サバ
- サンマ
- アジ
これらの青魚は、不飽和脂肪酸を多く含むうえに、比較的手に入りやすい魚です。
また、水煮缶などの加工品は保存性が高く、手軽に取り入れられるのが魅力です。忙しい日でも活用しやすいため、日々の食事に無理なく取り入れてみましょう。
7位…ナッツ

ナッツ類は糖質が少なく、食物繊維や良質な脂質を含む食品のため、間食として菓子類の代わりに取り入れるのがおすすめです。
さらに、ナッツに含まれる油脂は不飽和脂肪酸が豊富であり、菓子類のように飽和脂肪酸が多い食品と置き換えることで、脂質バランスの改善にも役立ちます。
■おすすめのナッツ類
- アーモンド
- カシューナッツ
- クルミ
- ピーカンナッツ
- ピスタチオ
ナッツを選ぶ際のポイントとして、ナッツ類を摂る際は、油で揚げていない「素焼き」のものや無塩タイプを選ぶのが理想的です。塩分の過剰摂取を防ぎ、健康的に取り入れることができます。
ナッツは栄養価が高い一方、脂質を多く含みカロリーも高いため、食べ過ぎには注意が必要です。
1日あたり15~20g程度までを目安に、適量を意識して取り入れましょう。
8位…果物

果物は糖類を含むため、糖尿病では控えるべきと思われがちですが、食物繊維や抗酸化成分が豊富で、適量を守れば糖尿病リスクの低減にもつながることが知られています。
特に、ブルーベリー、りんご、ぶどうは糖尿病発症リスクの低下に関連することが報告されており、適切に取り入れると良いでしょう。
果物はお菓子の代わりの間食として活用することで、砂糖や脂質の摂取を抑え、カロリーコントロールにも役立ちます。
ただし、果物ジュースは食物繊維が取り除かれ、糖類の吸収が早まるため、逆に糖尿病リスクを高める可能性があるとされています。果物は生のまま食べるのが理想的です。
果物の摂取量については個人の状態によりますが、1日100g程度までなら血糖値や血中中性脂肪値の改善が期待でき、体重増加にもつながりにくいと報告されています。
例として、りんご1/2個、バナナ1/2本、みかん1個程度が目安となります。
ただし、過剰摂取は血糖値の急上昇や肥満のリスクにつながるため、食事全体のバランスを考えながら適量を守ることが重要です。
糖尿病の方にもおすすめのレシピの紹介
糖尿病の方におすすめの食材を取り入れたレシピを紹介します。
食事療法のひとつのアイデアとして、ぜひ作ってみてくださいね。
たっぷりキノコの麦入り炊き込みご飯
分量(作りやすい量・6膳分)
- 白米…2合(300g)
- 押し麦…100g
- しめじ…1/2パック(50g)
- 舞茸…1/2パック(50g)
- えのきたけ…1/2パック(100g)
- 油揚げ…1枚(20g)
- 顆粒和風だし…小さじ1(3g)
- 醤油…大さじ3(54g)
- みりん…大さじ3(54g)
- 水…500ml
作り方
- 白米は洗ってザルに上げ、30分ほどおいて吸水させておく。
- しめじと舞茸は一口サイズにほぐす。えのきたけはほぐして2cmの長さに、油揚げは1cm角に切る。
- 炊飯器の釜に白米、押し麦、調味料、水を加えてざっと混ぜる。
- きのこ類と油揚げを米の上に乗せるように加えて炊飯する。
栄養価とコメント
- カロリー…278kcal
- たんぱく質…6.6g
- 脂質…2.0g
- 炭水化物…58.7g
- 食物繊維…2.8g
- 食塩相当量…1.5g
キノコや押し麦など、食物繊維の多い食材を取り入れた炊き込みご飯です。
たっぷりのきのこでかさ増しして、お米の量が少なくても食べごたえも満点です。
押し麦(もち麦でも可)は米よりも多くの水分を含むので、わずかながらかさ増し効果も期待できます。
カロリー控えめの主菜、野菜たっぷりの副菜と合わせて健康的な食事にしてくださいね。
血糖値を下げる生活習慣
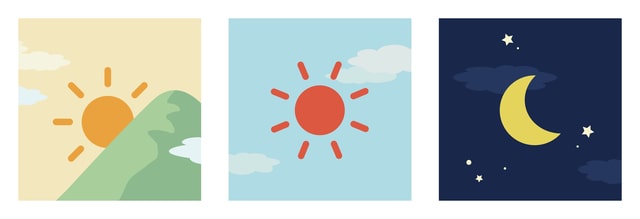
糖尿病の予防・治療には、食事内容だけでなく、いつ・どのように食べるかなどの食べ方や、暮らし方などの生活習慣も深く関わっています。
食事そのもの以外のポイントを紹介します。
規則正しい生活
規則正しい食事習慣は血糖値を安定させることに繋がります。
朝食抜きや夜食の習慣は、肥満や血糖値の乱れを引き起こしやすい要因とされています。
特に、長時間の空腹状態の後にまとめて食べると、血糖値が急上昇しやすくなるため、食事のリズムを整えることが重要です。
■規則正しい生活を目指すためのポイント
- 朝・昼・夕の3食を規則正しくとる
- 食事のボリュームが極端に偏らないようにする(特に夜に食べ過ぎない)
- 長時間の空腹を避ける(適度な間食を活用)
- 食事の時間をあらかじめ決め、習慣化する
- 朝食の時間を確保するために、夜は早めに就寝する
- 寝る直前の食事を避け、できるだけ就寝2~3時間前までに夕食を終える
まずは、できることから少しずつ改善し、食事リズムを安定させることを意識しましょう。
食べる順番・速さを意識する
食べる順番・速さを意識することで、食べ過ぎを防ぎ、血糖値の急上昇を抑える効果が期待できます。
満腹感が得られるまでには時間がかかるため、よく噛んでゆっくり食べる習慣をつけることが大切です。
- 会話を楽しみながら食べる(一口ずつしっかり噛む)
- 噛み応えのある食材を取り入れる(根菜類、きのこ類など)
- 一口の量を意識して減らし、箸を置く時間を作る
また、最初に野菜を食べる「ベジファースト」を心掛けると、血糖値の上昇を抑え、HbA1cの低下や体重管理にも効果が期待できます。
■ベジファーストの食べ方(順番)
- 野菜や海藻、きのこ類のおかず(副菜)…1食あたり100~150gを目標にする
- 肉・魚・卵・大豆製品のおかず(主菜)
- ごはん・パン・麺類などの主食(炭水化物)
この順番で食べることで、食物繊維をしっかり確保し、糖質の吸収を穏やかにする効果が期待できます。また、主食の食べ過ぎを防ぐことにもつながります。
ただし、食べる順番にこだわりすぎず、食事の前半に野菜やたんぱく源を意識して食べ、後半に主食をとるといった工夫でも十分効果が得られます。
外食・コンビニ食・おやつの選び方
外食やコンビニ食は高カロリーになりやすく、炭水化物が多め、野菜が不足しがちな傾向があります。そのため、無意識に選ぶと糖尿病の改善には適さない食事になりやすいといえます。
しかし、メニューの選び方を工夫することで、血糖値管理に適した食事を実現できます。
■外食・コンビニ食の選び方のポイント
- 栄養成分表示を確認し、カロリーの摂り過ぎを防ぐ
- 主菜・副菜・主食をそろえ、栄養バランスを意識する
- 「ご飯少なめ」や「小盛り」が選べる場合は活用する
- 「野菜たっぷり」「食物繊維が豊富」などのメニューを選ぶ
- 単品メニューの場合は、野菜のおかずを追加する
近年は健康志向の高まりにより、外食やコンビニでも栄養バランスを意識したメニューが増えているため、上手に活用して負担を減らしながら食事管理を続けていきましょう。
また、間食・おやつは、種類や量によってカロリーや炭水化物、脂質の過剰摂取につながるため、適量を意識することが大切です。
目安として1日100~200kcal以内が適切とされていますが、個人の体調や食生活に応じて調整するとよいでしょう。
■間食の選び方のポイント
- 量・頻度を控えめにする
- 砂糖や油脂分の多いものを避け、カロリーの低いものを選ぶ
- 食物繊維が豊富な食品を選ぶ
- 低GI食品を取り入れる
低カロリー甘味料を活用することで炭水化物やカロリーを抑えられますが、過剰摂取は間接的に生活習慣病リスクを高める可能性があることが知られているため、注意が必要です。
適度な身体活動
食事療法に運動療法を組み合わせることで、糖尿病のリスクをより効果的に抑えられることが知られています。
運動には、消費カロリーを増やして肥満を解消するだけでなく、インスリンの働きを改善する効果があり、血糖コントロールに役立ちます。
糖尿病の改善には、有酸素運動とレジスタンス運動(筋トレ)を組み合わせることが推奨されており、どちらも血糖値の改善に効果的とされています。
■運動の目安(糖尿病診療ガイドライン2019より)
- 楽にできる運動から始め、徐々に強度を上げる
- 1日10~30分以上、週3回以上、合計週150分以上
- 運動をしない日を2日以上続けない
- 自重トレーニングや器具・マシンを使用
- 10~15回×1セットから始め、8~12回×1~3セットに負荷を上げる
- 週2~3回、連続しないように行う
また、運動が難しい場合でも、日常生活の中で座りっぱなしを避け、こまめに体を動かすことで血糖値のコントロールに役立ちます。
- 30分に1回は立ち上がって体を動かす
- 歩く時間を増やす(バス停は1つ分歩く、買い物時に遠回りするなど)
- エレベーターやエスカレーターではなく階段を使う
- 座る時間を減らし、立って作業をする
運動を行う際は、合併症の有無や体の状態を考慮し、無理のない範囲で実施しましょう。
具体的な運動内容は医師や専門家と相談の上で決めることをおすすめします。
まとめ
糖尿病は自覚症状がないまま進行し、重大な合併症や命に関わる病気へとつながる可能性がある疾患です。
しかし、早期に血糖コントロールに取り組むことで、健康な状態を長く維持することが可能です。
糖尿病の管理に役立つ食べ物
糖尿病の食事では、血糖値の安定や栄養バランスの改善に役立つ食品を適量取り入れることが重要です。
- 低カロリーで食物繊維が豊富な野菜・海藻・きのこ
- 主食の中でも食物繊維を多く含む全粒穀物
- 肉類の代替として脂質のバランスを改善できる魚や大豆製品
- お菓子の代わりに適した果物やナッツ
ただし、これらの食品を多く摂れば摂るほど良いわけではなく、適量を守りながらバランスよく取り入れることが大切です。
また、食事の改善に加え、毎日の生活の中で体を動かす時間を増やすことや、規則正しい生活を意識することも血糖コントロールに役立ちます。
すべてを一度に変えるのは難しいため、できることから少しずつ取り入れ、無理なく続けることが成功のポイントです。
まずは身近なことから始め、健康的な習慣を少しずつ増やしていきましょう。
参考文献
厚生労働省:「日本人の食事摂取基準(2020年版)策定検討会」 報告書
文部科学省:「食品成分データベース:日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
社団法人日本栄養士会監修:「食事バランスガイド」を活用した栄養教育・食育実践マニュアル.第一出版,2011.
厚生労働省:「健康日本21(第2次)の推進に関する参考資料」
記事監修

院長 内田 智之
- 日暮里・三河島内科クリニック 院長
- 日本内科学会総合内科専門医
- 日本血液学会血液専門医
- 日本血液学会血液指導医
- ICLSディレクター
- がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修修了
- 難病指定医

管理栄養士 土肥 加奈
2012年に管理栄養士資格を取得後、ドラッグストアに勤務し、登録販売者の資格も取得しました。
医薬品やサプリメント、栄養に関する包括的な健康相談に従事し、現在はクリニック専門のホームページディレクターとして活動しています。








