脂肪肝にいい食べ物とは?脂肪肝改善におすすめの食事をランキングで紹介
脂肪肝は、現代の食生活や生活習慣の影響で多くの人が抱える健康問題のひとつです。
発症には食事や生活習慣が大きく関与しており、予防や改善のためにはこれらを見直すことが欠かせません。
この記事では、脂肪肝の改善に役立つ食べ物を中心に紹介するとともに、脂肪肝を引き起こす食習慣や生活習慣、そして改善のために取り組むべき食事療法のポイントについて解説します。
脂肪肝と診断されて食生活の見直しを検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。
脂肪肝とは?
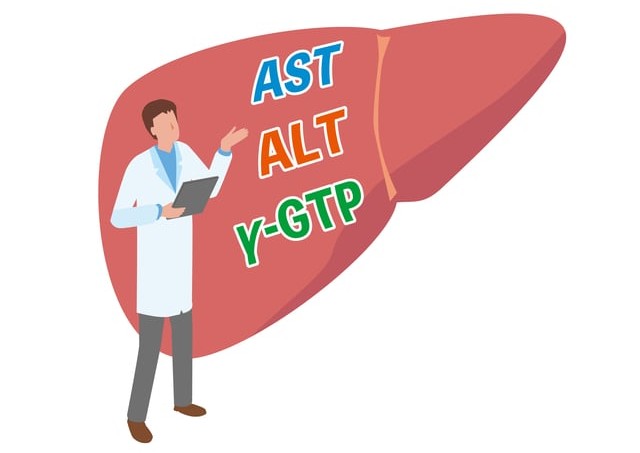
脂肪肝とは、肝臓の細胞に中性脂肪が過剰に蓄積した状態を指します。
発症原因の違いによって、アルコール性と非アルコール性に分類されますが、どちらも放置すると重篤な病気へと進行し、命に関わる可能性があります。
そのため、種類を問わず早期の対処が重要です。
脂肪肝の種類
脂肪肝はその原因にアルコールが含まれるか否かによってアルコール性脂肪肝と非アルコール性脂肪肝炎の2つに分類されます。
アルコール性脂肪肝は、過度なアルコール摂取が長期間(5年以上)続くことによって肝細胞内に脂肪が蓄積して肝障害を起こしたものです。
一方、非アルコール性脂肪肝はアルコール摂取とは無関係に、過剰なカロリー摂取、肥満、運動不足、生活習慣病などが主な原因となって引き起こされるものです。
脂肪肝の診断
脂肪肝の診断は血液検査、画像診断や組織学的診断によって行われます。
- 血液検査…AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTPなど
- 画像診断…腹部超音波検査、腹部CT検査、腹部MRI検査など
- 組織学的診断…肝生検
これらの検査により、肝臓に脂肪が蓄積していることが確認されると、脂肪肝と診断されます。
そのうえで、以下のような場合にアルコール性脂肪肝と診断されます。
- 1日の平均アルコール摂取が60g以上の状態が5年以上続いている(女性等では40g程度の場合も)
- 禁酒によって数値の改善がみられる
- 肝炎ウイルス等の原因が見られない
一方、過度のアルコール摂取や薬物性肝障害、遺伝子疾患による二次性脂肪肝でないことが確認されると、非アルコール性脂肪肝と診断されます。
非アルコール性脂肪肝では、飲酒量は純アルコール量で男性30g、女性20g程度までが当てはまるようです。
脂肪肝を放置するリスク
脂肪肝は初期段階では自覚症状がありませんが、放置すると次のような深刻な病気へ進展する可能性があります。
- アルコール性脂肪肝炎(ASH)
- 非アルコール性脂肪肝炎(NASH)
- 肝硬変
- 肝臓がん
脂肪肝が進行して肝臓に炎症が起こると「アルコール性脂肪肝炎(ASH)」「非アルコール性脂肪肝炎(NASH)」に移行し、肝細胞がダメージを受け、肝機能が低下します。
炎症や損傷が慢性的になると、肝組織が繊維化し「肝硬変」となり、硬くなった組織は元に戻りません。
さらに進行すると、肝臓がんのリスクが高まります。
加えて、脂肪肝は肝機能を低下させるだけでなく、インスリンの働きを妨げるため、2型糖尿病のリスクを高めます。
また、心臓病や脳卒中といった心血管疾患の発症リスクも増加することが知られています。
脂肪肝のリスク要因
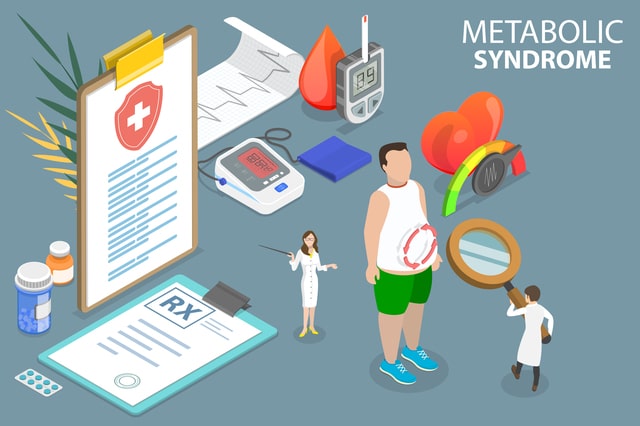
脂肪肝の主な原因は複数ありますが、多くは生活習慣に関連しています。
■脂肪肝の主な原因
- 過度のアルコール摂取
- 肥満(特に内臓脂肪型肥満)
- 糖尿病(インスリン抵抗性)
摂取カロリーが過剰で肥満状態にある人は、肝臓にも脂肪が蓄積しやすく、脂肪肝のリスクが高まります。
特に内臓脂肪型肥満は脂肪肝を引き起こしやすいとされています。
また、肥満でなくてもアルコールや糖質・脂質の過剰摂取は肝臓に脂肪を溜め込む要因となります。
さらに、肥満に関連してインスリンの働きが低下すること(インスリン抵抗性)により、血糖値が高い状態が続き、肝臓に脂肪が蓄積されやすくなります。
脂肪肝は肥満や糖尿病などの生活習慣病と密接に関わっており、食生活の見直しによって脂肪肝の改善だけでなく、これらの生活習慣病の予防・改善にもつながります。
脂肪肝改善のための食事のポイント

脂肪肝の改善には、生活習慣の見直しが欠かせませんが、その中でも食事が重要なポイントとなります。
まず、肥満解消のためにカロリー管理を行い、特に油脂分や糖類の摂取を控えることが基本です。
さらに、アルコールの摂取を制限することも重要な食事管理の一つです。
ただし、単に食事量を減らすだけでは、たんぱく質などの必須栄養素が不足し、栄養バランスが崩れてしまいます。
そのため、必要な栄養素を適量しっかりと摂取しながら、健康的な食生活を心がけることが大切です。
肥満解消
肥満や過剰なカロリー摂取は血中脂質を増加させ、肝臓に脂肪が蓄積する原因となります。
そのため、脂肪肝の改善には、カロリー管理による肥満解消が欠かせません。
具体的には、日々の消費カロリーよりも摂取カロリーを抑え、蓄積した体脂肪が少しずつ消費されるよう管理します。
体脂肪1kgは約7200kcalに相当し、短期間での消費は難しいため、食事と運動を組み合わせ、無理のないペースで継続的に取り組むことが大切です。
さらに、カロリー制限の適切な量は年齢や体格、活動量によって異なるため、医師や管理栄養士に相談し、自分に合った計画を立てることがポイントです。
長期的かつ健康的なダイエットを心がけ、脂肪肝の改善につなげましょう。
脂質を控える
肝臓に脂肪が蓄積する主な原因の一つが、脂質の過剰摂取です。
脂質は体に必要な必須栄養素ですが、現代の食生活では摂り過ぎになりやすいため、適量を意識することが大切です。
■脂質を控えるポイント
- 揚げ物を控える
- 脂身の多い肉類(鶏皮、バラ肉など)を控える
- 脂質の多い乳製品(バター、生クリームなど)を控える
これらの食品を完全に断つ必要はありませんが、続けて食べたり、大量に摂取することは控えましょう。
脂質は1gあたりのカロリーが高いため、適量に抑えることで食事全体のカロリーを抑え、体重管理にも効果的です。
砂糖を控える
砂糖類の過剰摂取も肝臓への脂肪蓄積の大きな原因となります。
特に、砂糖を多く含むお菓子や甘い飲料は、必須栄養素がほとんど含まれていないため、脂肪肝の改善を目指す方には控えるべき食品です。
■砂糖類を多く含む代表的な食品
- お菓子、ケーキ、アイスクリーム
- 菓子パン
- 嗜好飲料(ジュース、炭酸飲料など)
- ジャム、果物のシロップ漬け
- 砂糖、はちみつ、メープルシロップなどの甘味料
これらの食品を控えることで必要な栄養素は減らさずに摂取カロリーを抑えやすくなり、肥満解消にもつながります。
飲酒を控える
アルコールの過剰摂取は脂肪肝の大きな原因となるだけでなく、アルコールを原因としない非アルコール性脂肪肝でも、肝臓への脂肪蓄積を促進させる要因となります。
そのため、アルコール性・非アルコール性いずれの場合も脂肪肝の改善にはアルコールの摂取を控えることが重要です。
脂肪肝の食事療法では、基本的に禁酒が推奨されます。
また、アルコールはカロリーを含むため、禁酒することで摂取カロリーが減少し、肥満解消にもつながります。
無理なく禁酒を継続するためには、低カロリーなノンアルコール飲料を上手に活用すると良いでしょう。
たんぱく質は不足しないようにする
脂肪肝の食事療法では、肥満解消のためにカロリー制限が必要ですが、必須栄養素であるたんぱく質が不足しないよう注意が必要です。
たんぱく質が不足すると、肝臓の修復機能が低下し、かえって脂肪の蓄積を促進する恐れがあります。
低脂質で高たんぱくな食品を活用することで、カロリーを抑えつつ、必要なたんぱく質を摂取することができます。
ただし、たんぱく質は多く摂れば良いわけではありません。
過剰摂取は逆効果になる場合もあるため、医師や管理栄養士の指導を受け、体調や状況に合った適量を心がけることが大切です。
脂肪肝にいい食べ物ランキング6選
脂肪肝の改善には、食事の見直しが非常に重要です。
世の中には「脂肪肝に良い食べ物」としてさまざまな情報が広がっていますが、食べるだけで脂肪肝が改善する、いわゆる薬のような効果を持つ食べ物は存在しません。
脂肪肝に良い食べ物とは、脂肪肝の悪化を防ぎ、食事療法をサポートする食品と考えましょう。
■脂肪肝の改善に役立つ食品の特徴
- 低脂質、高たんぱく質
- 低カロリーで食事量を増やせる
- 食物繊維が豊富
- お酒の代替になる
ここからは、これらの特徴を持つ食品をランキング形式でご紹介します。
これらは「食べるほど肝臓に良いもの」ではないため、食事療法の負担を軽減するために上手に取り入れることが大切です。バランスの良い食事の一部として、ぜひ活用してみてください。
1位 鶏肉

鶏肉、特に皮を取り除いた鶏むね肉や鶏ささみは、ダイエットの定番食材で脂肪肝の改善にも役立つ代表的な食材です。
これらは肉類の中でも脂質が少なく、良質なたんぱく質をの摂取に適した組成が特徴です。
■鶏むね肉と鶏ささみ肉の栄養成分値(100gあたり)
| 食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|
| 鶏むね肉(皮なし) | 105kcal | 23.3g | 1.9g |
| 鶏ささみ | 98kcal | 23.9g | 0.8g |
出典:文部科学省「食品成分データベース:日本食品標準成分表2020年版(八訂)」
鶏むね肉やささみはクセが少なく、さまざまな料理に使いやすい点も魅力です。
さらに、価格も比較的安価なため、日常の食事に手軽に取り入れやすい食材と言えるでしょう。
2位 豆腐・納豆

豆腐や納豆などの大豆製品も低脂質・高たんぱくな食材として優れています。
特に納豆は、たんぱく質だけでなく食物繊維も豊富に含まれており、動物性食品と植物性食品の良い点を併せ持つ食材です。
■大豆製品の栄養成分値(100gあたり)
| 食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 食物繊維 |
|---|---|---|---|---|
| 木綿豆腐 | 73kcal | 7.0g | 4.9g | 1.1g |
| 絹ごし豆腐 | 56kcal | 5.3g | 3.5g | 0.9g |
| 納豆 | 184kcal | 16.5g | 10.0g | 9.5g |
出典:文部科学省「食品成分データベース:日本食品標準成分表2020年版(八訂)」
また、豆腐は低カロリーでありながら満足感が得られるため、カロリー制限中の食事でもボリュームを増やしやすい点が魅力です。
日々の食事に取り入れることで、栄養バランスを整えながら脂肪肝の改善に役立てることができます。
3位 野菜

野菜類は、低カロリーでありながら、ビタミン・ミネラル・食物繊維といった必須栄養素を豊富に含む食材です。
食事のボリュームを増やしながらカロリーを抑えられるため、脂肪肝の改善のために肥満解消を目指す方に最適です。
カロリーオフと食事のかさ増しが目的の場合は、生野菜を使ったサラダがおすすめです。
一方で、ビタミン・ミネラル・食物繊維をしっかり摂りたい場合には、スープや煮物など加熱調理をすることで量を多く食べやすくなります。
目安として、可能であれば毎食1〜2品取り入れ、1日合計で約350g程度を摂取できると理想的です。
4位 精製度の低い穀類(玄米など)

玄米、雑穀米、麦飯といった精製度の低い穀類(全粒穀類)を積極的に取り入れるとよいでしょう。
穀類は炭水化物という必須栄養素の供給源ですが、摂りすぎるとカロリーや糖質の過剰摂取につながりやすいため、脂肪肝の方は注意が必要です。
■精製度の低い穀物の例
- 玄米…もみ殻だけを取り除いた未精米のお米
- 雑穀米…オオムギ、アワ、ヒエ、キビなどの雑穀類を混ぜたもの
- 麦飯…押し麦やもち麦を加えたご飯
これらを使用したご飯は、精白米のごはんに比べて食物繊維が豊富です。
カロリー自体はほぼ同じですが、糖の吸収を遅らせる効果があり、また、より満腹感を得やすいというメリットがあります。
■穀類の栄養成分(調理前100gあたり)
| 食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 食物繊維 |
|---|---|---|---|---|
| 精白米 | 342kcal | 6.1g | 0.9g | 0.5g |
| 玄米 | 346kcal | 6.8g | 2.7g | 3.0g |
| キビ | 353kcal | 11.3g | 3.3g | 1.6g |
| アワ | 346kcal | 11.2g | 4.4g | 3.3g |
| ヒエ | 361kcal | 9.4g | 3.3g | 4.3g |
| 押し麦 | 329kcal | 6.7g | 1.5g | 12.2g |
出典:文部科学省「食品成分データベース:日本食品標準成分表2020年版(八訂)」
雑穀米や麦飯は、混ぜる穀類の種類や分量によって栄養成分が異なります。
あらかじめミックスされた市販品を利用する際は、栄養成分表示でカロリーや食物繊維量を確認すると確実です。
5位 海藻・きのこ

海藻類やきのこ類も野菜類と並んで低カロリーな食材であり、食物繊維の摂取源となる食品です。
野菜類と同様、食事のボリュームを増して満足感を高め、摂取カロリーを抑えるのに役立ちます。
海藻類は乾燥品が多く、きのこは冷凍保存が可能なことから、買い置きができて便利な食材でもあります。
野菜と合わせて毎食1~2品、1日あたり野菜・海藻・きのこを合計で350g摂取することを目指しましょう。
6位 ノンアルコール飲料

ノンアルコール飲料は、アルコールを摂取せずにお酒の楽しさや雰囲気を味わえるため、脂肪肝の食事療法に適した選択肢の一つです。
脂肪肝には、アルコール過剰摂取が原因のケースと、そうでないケースがありますが、どちらの場合でもアルコールの摂取は肝臓に負担をかけ、脂肪肝のリスクを高めるため、飲酒量を減らすことが重要です。
ノンアルコール飲料を活用すれば、禁酒によるストレスを軽減しつつ、肝臓への負担を抑えられます。
ただし注意点として、ノンアルコール飲料には糖質が多く含まれるものもあります。
糖質由来のカロリーが高い製品を選ぶと、結果的に糖質過多となり、肝臓に悪影響を及ぼす可能性があります。
そのため、ノンアルコール飲料を選ぶ際は栄養成分表示を確認し、アルコールだけでなく糖質も控えめなものを選ぶことが大切です。
脂肪肝改善のための生活習慣のポイント

食事以外の生活習慣の見直しも脂肪肝の改善に役立つことが知られています。
食事改善と合わせて取り組みたい生活習慣のポイントを紹介します。
適度な運動
適度な運動は体重減少の有無にかかわらず肝臓脂肪化の改善につながることが知られています。
具体的な運動内容について決まった基準はありませんが、運動によって肝脂肪化の改善効果が得られたとする研究報告では以下のような内容であったことが報告されています。
- 1回あたり30~60分、週3~4回の運動習慣を1~3ヶ月程度
- 週に250分以上、中等度~強度の有酸素運動でより効果的
- 筋トレも有酸素運動と同様に肝脂肪化を改善する
とはいえ、これまで運動習慣のなかった人にとっては、毎週250分以上の運動を行うことは簡単ではありません。
まずは無理をせず、少しでも体を動かす時間を増やすように意識することから始めるのが良いでしょう。
座りっぱなしの時間を減らすように立って動くことを意識する、歩く距離を増やしたり、意識して階段を使うなど、生活の中で体を動かす機会を増やすことが大切です。
規則正しい生活
脂肪肝の主要な原因のひとつである肥満の解消には、規則正しい生活も重要なポイントです。
脂肪肝との直接の関連は見出されていないものの、睡眠不足や睡眠のとり過ぎ、朝食の欠食は肥満につながりやすいことが報告されています。
夜遅くまで起きる生活では夜食などの余分なカロリー摂取に繋がりやすく、また、夜更かしによって寝不足になると朝食の欠食に繋がります。
朝食を食べない生活スタイルでは身体活動が少なくなる傾向があり、カロリー消費が少なくなってしまいます。
太りにくい体を作るために、以下のようなポイントを意識しましょう。
- 十分な睡眠時間の確保のため、早めに就寝する
- 早起きをして朝食を食べる
- スムーズな入眠のため、入浴でリラックスする
- 就寝前2時間以内の食事は避ける
規則正しい生活を意識することで、肥満の予防・改善に役立ちます。
食事の見直しや運動と合わせて取り入れてみてくださいね。
まとめ
脂肪肝は、肝臓に脂肪が蓄積した状態で、放置すると肝炎や肝硬変に進行し、さらには肝がんなど重大な病気を引きおこす可能性があるため、早期の改善が求められます。
改善には、肥満解消のためのカロリー管理や、脂質・糖質の過剰摂取を控えること、アルコール摂取の制限が欠かせません。
こうした食事管理を続けるためには、低カロリーな食材、低脂質・低糖質な食品、アルコール代替品が便利です。これらの食品を上手に取り入れることで、毎日の食事療法のハードルを低くすることができます。
ただし、自己流で食事療法を進めるのは難しく、健康を損なうリスクもあるため、医師や管理栄養士の指導を受けながら、自分の体に合った食事内容を実践することが大切です。
参考文献
日本消化器病学会:「NAFLD/NASH診療ガイドライン2020」
アルコール医学生物学研究会:「JASBRA アルコール性肝障害診断基準 2011年版(2021年小改訂)」
文部科学省:「食品成分データベース:日本食品標準成分表2020年版(八訂)」
Luyster FS, Strollo PJ Jr, Zee PC, Walsh JK; Boards of Directors of the American Academy of Sleep Medicine and the Sleep Research Society. Sleep: a health imperative. Sleep 35: 727-734, 2012.
Smith KJ,et al. Skipping breakfast:longitudinal associations with cardiometabolic risk factors in the childfood Determinants of Adult Hearth Study.Am J Clin Nutr 2010;92:1316-25.
記事監修

院長 内田 智之
- 日暮里・三河島内科クリニック 院長
- 日本内科学会総合内科専門医
- 日本血液学会血液専門医
- 日本血液学会血液指導医
- ICLSディレクター
- がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修修了
- 難病指定医

管理栄養士 土肥 加奈
2012年に管理栄養士資格を取得後、ドラッグストアに勤務し、登録販売者の資格も取得しました。
医薬品やサプリメント、栄養に関する包括的な健康相談に従事し、現在はクリニック専門のホームページディレクターとして活動しています。








