血圧を下げる食べ物5選。高血圧改善に良い食事選び・食べ方のコツを解説
高血圧は糖尿病、脂質異常症などと並ぶ生活習慣病の一つであり、放置するとさらなる重大な病気につながるおそれがあります。
高血圧の発症には食事を含む生活習慣が大きく関わっており、予防のためには毎日の食事内容を見直すことが効果的です。
この記事では、高血圧改善のために取り入れたいおすすめの食材や、無理なく続けられる食事療法のポイントを詳しく解説します。
また、高血圧の方におすすめの減塩レシピ、そのほか食事以外にも生活習慣改善ポイントもご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
高血圧の診断基準と治療
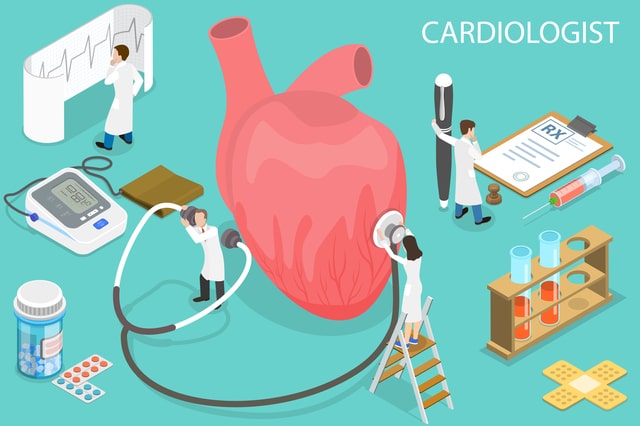
血圧は、血管の内側にかかる圧力を示すもので、心臓が血液を送り出す瞬間の「収縮期血圧(上の血圧)」と、心臓が拡張している間の「拡張期血圧(下の血圧)」の2つの数値で表されます。
高血圧は、この収縮期血圧や拡張期血圧のどちらか、または両方が正常値を超えた状態を指します。
特定健康診査(メタボ健診)では、収縮期血圧が130㎜Hg以上、または拡張期血圧が85㎜Hg以上で高血圧と判断されます。
■日本人間ドック学会 2023年度判定区分表
| 血圧区分 | 収縮期血圧 | 拡張期血圧 |
|---|---|---|
| 正常 | 129㎜Hg以下 | 84㎜Hg以下 |
| 軽度異常 | 130~139㎜Hg | 85~89㎜Hg |
| 要経過観察 | 140~159㎜Hg | 90~99㎜Hg |
| 要医療 | 160㎜Hg以上 | 100㎜Hg以上 |
高血圧は症状に乏しく、初期段階では自覚症状がほとんどありませんが、進行すると頭痛、めまい、胸の圧迫感などが現れることがあります。
高血圧を放置して血管への負荷が長期間続くと、血管だけでなく心臓、脳、腎臓などにダメージを与え、動脈硬化、心血管疾患、脳血管疾患、腎機能低下や腎不全のリスクを高めます。
これらの疾患の中には命に関わるものも多く含まれるため、高血圧が軽度なうちに治療を始め、進行を防ぐことが非常に重要です。
高血圧の治療は、生活習慣の見直しと降圧薬を使用する薬物療法に分けられます。
生活習慣の見直しは食事、運動、飲酒の制限などによるもので、薬物治療の有無にかかわらず必要になることから、高血圧の治療のために特に重要なものと言えます。
高血圧のリスク要因と食事の改善ポイント

高血圧の発症には、遺伝素因のほか、生活習慣における問題が関係しています。
高血圧のリスクになる生活習慣のうち、食事にかかわるものには以下のようなものがあります。
- 肥満
- 食塩の過剰摂取
- アルコールの過剰摂取
それぞれのリスク要因を改善することにより、高血圧の進行を防ぐことに繋がります。
また、リスクとなる食事の改善とは別に、高血圧を抑制する方向に働く栄養素(カリウム、カルシウム、食物繊維)を積極的にとることも高血圧の改善に役立ちます。
肥満
肥満は高血圧の主要なリスク要因のひとつです。
摂取カロリーが消費カロリーを上回ると、余剰カロリーが体脂肪として蓄積され、体重が増加します。
肥満と判断されるのは身長と体重から計算される体格指数(BMI)が25以上の場合で、BMIが25~30の肥満者は、BMIが20未満の人に比べて高血圧を発症するリスクが高いことが知られています。
肥満では、体内のホルモン分泌量やその働きが変化することがあり、これが血圧上昇の要因となります。
具体的なメカニズムとしては、血管が収縮しやすくなったり、ナトリウムの排出が抑えられたり、交感神経が過剰に刺激されたりすることで血圧が上昇すると考えられています。
さらに、肥満は高血圧だけでなく、糖尿病や脂質異常症といった他の生活習慣病のリスク要因でもあります。
これらの病気が併発すると動脈硬化を進行させ、高血圧とともに将来的な健康リスクを高めるため、肥満解消を目的としたカロリー管理は健康維持のために重点的に取り組むべき課題です。
食塩の過剰摂取
食塩(ナトリウム)は、過剰摂取すると血液中の水分量を増やす作用があり、血管内の圧力を高めることで血圧を上昇させる原因となります。
日本高血圧学会が発表している「高血圧治療ガイドライン2019」では、減塩の目標値として1日6g未満が推奨されています。
しかし、現代の日本の食生活では、多くの人がこの目標値を大きく上回っていることが知られており、男性で平均14g、女性で11g程度の塩分を摂取しているとも報告されています。
そのため、高血圧の人はもちろん、血圧に問題がない人にとっても、減塩は健康維持のために必要な取り組みといえるでしょう。
アルコールの過剰摂取
アルコールには血管を収縮させたり交感神経を刺激したりする作用があることから、過剰な飲酒は高血圧の原因となることが知られています。
飲酒量を適度に抑える「節酒」により血圧を下げる効果が期待でき、飲酒制限は1~2週間という比較的短い期間でも効果があると報告されています。
高血圧がある場合の飲酒制限は、、純アルコール摂取量を男性は1日20~30ml以下、女性はその半分の10~20ml以下にすることが推奨されています。
■純アルコール20~30mlに相当する酒量の目安
- ビール:中ビン1本(500ml)
- ワイン:2杯(250ml)
- 日本酒:1合(180ml)
- 焼酎:半合(90ml)
- ウイスキー:ダブル1杯(60ml)
飲酒量を適切に管理することで、高血圧リスクを抑え、長きにわたり健康的な生活を維持することにつながります。
カリウム、カルシウム、食物繊維の不足
カリウム、カルシウム、食物繊維といった栄養素はそれぞれの作用により高血圧を抑制することが知られています。
カリウムは体内のミネラルバランスを調整し、過剰に摂取したナトリウムの排出を促す働きがあります。
カリウムはさまざまな食品に含まれていますが、摂取カロリーを抑えつつ十分な量のカリウムを効率的に摂るには、低カロリーな野菜や果物が最適です。
ただし、高血圧に加えて腎臓機能の低下がありカリウムの摂取量を制限する必要がある場合には、医師等の指示のもと適切な食事内容を計画することが大切です。
カルシウムは血管の伸縮性の維持に関わる栄養素で、不足すると血圧上昇の原因になることが知られており、不足しないことが大切です。
カルシウムは牛乳・乳製品をはじめ、小魚類や野菜類がよい摂取源となります。
食物繊維は血圧への直接的な効果はないものの、肥満や動脈硬化の抑制につながる働きがあることから、間接的に血圧の低下に関わる栄養素です。
食物繊維は植物性食品に含まれ、特に精製度の低い穀類や野菜類、きのこ、海藻などが代表的です。
血圧を下げるためにおすすめの食べ物・飲み物
ここからは、血圧を下げるための食事療法に適した食べ物・飲み物の具体例を紹介します。
高血圧の改善に役立つカリウム、カルシウム、食物繊維が豊富な食品や、高血圧のリスクになりうる過剰のカロリー、食塩、アルコールを減らすのに役立つ食品となっていますので、毎日の食事にぜひ取り入れてみてくださいね。
野菜類

野菜類は、低カロリーであること、カリウムや食物繊維が豊富な点で高血圧の改善に役立つ食品です。
野菜の中でも色の濃い「緑黄色野菜」の中にはカルシウムを豊富に含むものもあり、積極的にとりたい食品の筆頭といえます。
■野菜類のカロリー・カリウム・食物繊維・カルシウム含有量(100gあたり)
| 食品名 | カロリー | カリウム | 食物繊維 | カルシウム |
|---|---|---|---|---|
| ほうれん草(生) | 18kcal | 690mg | 2.8g | 49mg |
| 小松菜(生) | 13kcal | 500mg | 1.9g | 170mg |
| 水菜(生) | 15kcal | 480mg | 3.0g | 210mg |
| ブロッコリー(生) | 35kcal | 460mg | 5.1g | 50mg |
| かぼちゃ(生) | 78kcal | 460mg | 3.5g | 22mg |
| ごぼう(生) | 58kcal | 320mg | 5.7g | 46mg |
| オクラ(生) | 15kcal | 280mg | 5.0g | 92mg |
色の濃い葉物野菜(例:ほうれん草、小松菜)は、低カロリーでカリウムを多く含む点が魅力です。
葉物野菜の一部(小松菜、水菜)はカルシウムを多く含むのも特徴です。
一方、根菜類(例:ごぼう、かぼちゃ)は、野菜の中ではややカロリーが高めですが、食物繊維が豊富に含まれています。
野菜類はどれか一つに偏るのではなく、いろいろな種類の野菜をバランスよく取り入れることをおすすめします。
果物類

果物類は、野菜と同様にカリウムの優れた供給源です。
果物は生で食べることが多いことから、調理によってカリウムが溶け出す心配がなく、効率的に摂取できる点が魅力です。
さらに、果物は高カロリーなお菓子類の代わりにすると間食からの摂取カロリーを抑えるのにも役立ちます。
■果物類のカロリー・カリウム・食物繊維含有量(100gあたり)
| 食品名 | カロリー | カリウム | 食物繊維 |
|---|---|---|---|
| アボカド | 176kcal | 590mg | 5.6g |
| バナナ | 93kcal | 360mg | 1.1g |
| メロン | 93kcal | 340mg | 0.5g |
| グリーンキウイ | 51kcal | 300mg | 2.6g |
| ゴールドキウイ | 63kcal | 300mg | 1.4g |
| ネーブルオレンジ | 48kcal | 180mg | 1.0g |
| みかん | 49kcal | 150mg | 1.0g |
アボカドはカリウムと食物繊維を非常に多く含む果物ですが、カロリーが高いため摂取量には注意が必要です。
一方、カロリー・カリウム・食物繊維のバランスが良いのはグリーンキウイで、1年を通して手に入りやすく価格も手頃なため、日常の食事に取り入れやすい果物といえるでしょう。
海藻類・きのこ類

海藻類やきのこ類も低カロリーでカリウム、食物繊維がとれることから、肥満や高血圧の改善に役立つ食品です。
■きのこ類・海藻類のカロリー・カリウム・食物繊維含有量(100gあたり)
| 食品名 | カロリー | カリウム | 食物繊維 |
|---|---|---|---|
| ぶなしめじ | 26kcal | 370mg | 3.0g |
| えのきたけ | 34kcal | 340mg | 3.9g |
| エリンギ | 31kcal | 340mg | 3.4g |
| なめこ | 21kcal | 240mg | 3.4g |
| まいたけ | 22kcal | 230mg | 3.5g |
| 乾燥わかめ(水戻し) | 20kcal | 440mg | 4.3mg |
| 干しひじき(茹で) | 11kcal | 160mg | 3.7mg |
きのこ類や海藻類は野菜と比較すると価格の変動が少なく、お手頃なのが魅力です。
野菜類と合わせて積極的にとりたい食品と言えます。
低脂肪の乳製品

カルシウムを十分に摂取することは血圧の低下に効果的であることが知られています。
乳製品はカルシウムの供給源の代表格であり、他の食品に比べても吸収率が高い点が魅力です。
■乳製品のカロリーとカルシウム含有量(100gあたり)
| 食品名 | カロリー | カルシウム |
|---|---|---|
| 普通牛乳 | 61kcal | 110㎎ |
| 低脂肪乳 | 42kcal | 130㎎ |
| ヨーグルト(全脂無糖) | 56kcal | 120㎎ |
| ヨーグルト(低脂肪無糖) | 40kcal | 130㎎ |
| ヨーグルト(無脂肪無糖) | 37kcal | 140㎎ |
| 飲むヨーグルト(加糖) | 64kcal | 110㎎ |
| プロセスチーズ | 313kcal | 630㎎ |
乳製品の中でも低脂肪のヨーグルトや牛乳は低カロリーであり、控えることが望ましいとされる飽和脂肪酸を抑えつつカルシウムを摂取するのに便利です。日々の食事に合わせて、乳製品を上手に活用しましょう。
チーズのように牛乳を濃縮した食品はカルシウム含有量が高い一方でカロリーも高くなりがちです。そのため、摂取量を調整しながら取り入れることが重要です。
ノンアルコール飲料

高血圧の管理には、アルコール摂取量を適正範囲内に抑える「節酒」が重要です。
お酒を模したノンアルコール飲料は、アルコールを控えながらもお酒の雰囲気を楽しむことができるため、飲酒量を減らすサポートとして活用できます。
ただし、ノンアルコール飲料の中には、砂糖類が多く含まれているものもあり、ジュースのような飲料では余分なカロリー摂取につながる可能性があります。
そのため、糖質が抑えられているカロリーオフやカロリーゼロの製品を選ぶのがおすすめです。
飲む量や頻度にも注意しながら、健康的な選択を心がけましょう。
魚介類

魚介類は肉類と替えて食べることを意識したい食材です。
高血圧の食事療法では、血圧へ直接関係しないものの、飽和脂肪酸を減らして多価不飽和脂肪酸を摂取することも推奨されています。
魚介類は肉類と比較して不飽和脂肪酸が比較的豊富であるため、日々の食事で摂取する機会を増やしたい食材です。
- 鮭
- いわし
- しらす
- さば
- サンマ
- アジ
これらの魚類は多価不飽和脂肪酸が多く、比較的手に入れやすく取り入れやすいのも魅力です。
しらす、煮干しのような小魚類は丸ごと食べることでカルシウムの摂取源にもなります。
塩分無添加のものを選ぶなど、塩分摂取量に気をつけながら取り入れるとよいでしょう。
植物油

植物油も、動物性の油脂と置き換える形で取り入れたい食材です。
植物油はバター、肉の脂身(ラードや牛脂も含む)などの動物性油脂と比較して飽和脂肪酸が少なく、不飽和脂肪酸が多い傾向があります。
動物性油脂と替えて植物油を選ぶことで、食事からの脂肪酸摂取バランスを整えることができます。
- サラダ油
- キャノーラ油(なたね油)
- オリーブオイル
- ごま油
- 大豆油
- 米油
とはいえ、植物油も油脂を抽出したものであり、重さあたりのカロリーはかなり高い食品です。
とり過ぎには注意しつつ、適量範囲で取り入れましょう。
減塩調味料・加工食品

近年、通常よりも食塩の含有量を抑えた「減塩調味料」が数多く販売されており、減塩を目指す方にとって頼もしい味方となっています。
同じ量を使用しても食塩の摂取量を抑えることができるため、健康管理に役立ちます。
■減塩タイプの調味料の例
- 醤油
- 味噌
- ソース
- ドレッシング
- ケチャップ
- ポン酢
- 顆粒だし(和風だし、中華だし、コンソメなど)
ただし、減塩調味料の中にはカリウムが多く含まれるものもあります。
腎機能が低下している方にはカリウム制限が必要な場合があるため注意が必要です。
使用前に医師や管理栄養士に相談すると安心して取り入れられます。
血圧低下のための減塩のポイント

高血圧の改善には、減塩が最も重要なポイントと言えます。
減塩には、調味料からとる塩分を減らすこと、加工食品からとる塩分を減らすことに分けられます。
また、単に食塩を減らすだけでは味が物足りなくなり、挫折してしまうことも少なくありません。
減塩しながらもおいしさを保つには、味付けの工夫や便利な市販品の活用が効果的です。
それぞれについて具体的なポイントを解説します。
できそうなものから徐々に取り入れて薄味に慣れていきたいですね。
調味料からとる塩分を減らす
調味料は塩分の主な摂取源です。
調味料由来の塩分をとりすぎないよう、食べ方に注意しましょう。
「卓上調味料はかけずにつける」ことを意識しましょう。
料理を盛り付けた後に加える調味料は、無意識のうちに食塩摂取量を増やす原因となることがあります。
具体例としては、刺身に使う醤油、餃子やシュウマイのたれ、揚げ物にかけるソース、サラダのドレッシング等が挙げられます。
これらの調味料を直接料理にかけるのではなく、小皿に少量取り、必要に応じてつけるようにすると塩分摂取量を抑えられます。
また、調味料をつける際は、全体にからませるのではなく、舌に触れる部分に少量つけるようにすると、調味料の味をしっかり感じられるため、少量でも満足感を得やすくなります。
「麺類のスープは残す」のも実施しやすいポイントです。
ラーメン、うどん、そばなどの麺類のスープは通常の汁物に比べて塩分濃度が高く、量も多いため、塩分過多の原因になりやすい食品です。
これらの麺類については食べる頻度を控えることに加えて、スープはできるだけ残すよう心がけましょう。
少しの意識で塩分摂取量を減らし、高血圧の予防や改善に役立てることができます。
加工食品からとる塩分を減らす
加工食品はその製造過程で塩分を添加されていることが多く、塩分の摂取源となっています。
特に漬物類や塩漬けの加工品は少量でも塩分摂取量が増えてしまうため、減塩を目指す場合には控えたい食品です。
- 漬物(ぬか漬け、たくあん、柴漬け、キムチなど)
- 梅干し
- 魚介加工品(干物、しらす干し、塩辛など)
- 魚卵加工品(たらこ、明太子、いくら醤油漬けなど)
塩分の摂りすぎを防ぐためには、これらの食品は毎日食べないよう量と頻度に注意しましょう。
また、惣菜類や外食に関しても、塩分が高い傾向があります。
栄養成分表示などを確認しながらなるべく塩分量の少ないものを選んだり、量や頻度を調整することを意識しましょう。
減塩しつつ美味しく食べるには
減塩しつつ美味しく食べるには、塩分を伴わない調味料や食材を活用すると良いでしょう。
具体的には、だし・酸味・香辛料・香味野菜を活用するのがおすすめです。
だしに含まれるうまみ成分(グルタミン酸、イノシン酸など)、お酢や柑橘類の酸味、香辛料(スパイス)や香味野菜(ハーブ)は塩分が少なくても味の満足度を高めてくれる効果があります。
■減塩に役立つ食品の例
- だし…昆布、鰹節、干し椎茸、貝類、肉類、エビ、カニなど
- 酸味…米酢、穀物酢、バルサミコ酢、レモン、ゆず、すだちなど
- 香辛料…こしょう、とうがらし、カレー粉、わさびなど
- 香味野菜・ハーブ…生姜、にんにく、しそ、みょうが、バジルなど
塩分は少なめに、上記の食材を組み合わせて取り入れることで美味しく減塩することに繋がります。
特にうまみ成分は2種類以上を併用することで相乗効果があるため、上手に取り入れるとよいでしょう。
顆粒の製品の場合は食塩が多く使用されている場合もありますので、栄養成分等を確認すると確実です。
市販品を活用する
塩分管理には便利な市販品の活用も効果的です。
先に紹介した減塩タイプの調味料や加工食品のほか、宅配食や宅配惣菜では、高血圧の方向けに1食単位で塩分量が調整されたメニューも販売されています。
1食あたりの栄養価・塩分量が計算されているだけでなく、調理や盛り付けも済んでいるため、調理の負担を大幅に軽減しつつ食事管理もできるのが魅力です。
また、冷凍タイプなら冷凍庫にストックしておくことで、食べたいときに食べたいメニューを選んで簡単に準備できます。
このような宅配食は、塩分管理が難しい方や忙しい一人暮らしの方に特におすすめです。
手軽に塩分を抑えた食事を取り入れられるため、健康的な食生活のサポートに役立ちます。
血圧を下げる食材を活用した簡単レシピ紹介
血圧を下げるために摂りたい食品を活用した簡単レシピを紹介します。
減塩レシピにもなっていますので、ぜひお試しください。
サーモンのレモンハーブ焼き
分量(1人分)
- 生鮭…80g
- ハーブソルト…小さじ1/2(0.9g)
- 小麦粉…小さじ1(3g)
- ブロッコリー…30g
- しめじ…30g
- オリーブオイル…大さじ1/2(6g)
- 白ワイン…大さじ1(15g)
- レモン汁…大さじ1/2(7.5g)
作り方
1.しめじは石づきを取ってほぐす。ブロッコリーは小房に分けて固めに茹でておく。
2.生鮭の両面にハーブソルトを振ってなじませ、小麦粉をまぶす。
3.フライパンにオリーブオイルをひいて熱し、温まったら鮭を身から焼く。
4.表面に焼き目がついたらひっくり返し、裏面も焼きめをつける。
5.フライパンの空いた場所にしめじ、ブロッコリーを加え、白ワインを加えて蓋をして蒸し焼きにする。
6..中まで火が通ったらレモン汁をふって皿に盛り付ける。
栄養価(1人分)
- カロリー…195kcal
- たんぱく質…20.2g
- 脂質…9.6g
- 炭水化物…6.6g
- 食塩相当量…1.1g
- カリウム…470mg
コメント
高血圧の食事に推奨される食材を活用した主菜メニューです。
多価不飽和脂肪酸が豊富な鮭をメイン食材にし、塩分少なめでも美味しく食べられるレモンハーブの味付けとしました。
ブロッコリーやきのこを加えることでボリュームとカリウム量を増しつつ、カロリーは控えめです。
ブロッコリーは下ごしらえ不要の冷凍ブロッコリーを活用するとより手軽に作れます。
高血圧改善のために気を付けたい生活習慣の改善ポイント

高血圧の改善には、食事以外に運動や喫煙といった生活習慣も関係しています。
高血圧を改善するために取り入れたい生活習慣の改善ポイントを紹介します。
適度な運動
運動不足は、高血圧の原因の一つであり、運動を習慣化することで、直接的に血圧を下げる効果が得られることが知られています。
そのほか、運動は消費カロリーを増やして肥満を改善することにもつながるため、積極的に生活習慣に取り入れることが大切です。
日本高血圧学会の「高血圧治療ガイドライン2019」では、速歩、ステップ運動、スロージョギング、ランニングなどの有酸素運動が推奨されています。
目標としては、これらの運動を毎日30分、または週合計180分以上行うことです。
もし、スポーツの時間をとることが難しい場合は、1日の中で体を動かす時間を増やすことを意識しましょう。
■効果的な身体活動の例
- 歩行(普通~速歩き)
- 階段の上り下り
- 自転車をこぐ
- 掃除や子どもの世話などの立ち仕事
- 荷物の持ち運びや積み下ろし
これらの動作が1日合計で60分以上になることを目標に、日常生活を見直してできることから取り組んでみましょう。
無理のない範囲で運動量を増やすことで、健康的な生活を目指せます。
禁煙
たばこには血管を収縮させたり心拍数を増加させたりする作用があり、これが血圧を上昇させる原因となります。
また、長期間の喫煙は動脈硬化を進行させ、さらに血圧を高めるリスクをもたらします。
禁煙が自己流では難しい場合は、禁煙補助薬を活用した禁煙指導などのサポートを積極的に利用するのがおすすめです。
専門的な支援を受けることで、禁煙の成功率を高めることができます。
なお、禁煙の過程で体重が増えるケースもあるため、食事のカロリー管理にも注意を払いましょう。
禁煙と健康的な体重維持を両立させることで、さらなる健康改善が期待できます。
ストレス対策
心理的・社会的ストレスや睡眠不足は、自律神経の働きを乱し、高血圧の発症や進行を引き起こす一因となります。
十分な休養を取るためには、まず睡眠時間をしっかり確保することが重要です。
早めに寝床に入るようにしたり、寝室や寝具を見直して快適な睡眠環境を整えることが効果的です。
体と心をしっかり休めるために、日々の生活習慣を見直し、リラックスできる環境を整えるよう心がけましょう。
寒さ対策
高血圧の方は寒さ対策にも気を配るようにしましょう。
寒い環境では血圧が上がることから、脳死血管疾患のリスクが高まることが知られています。
外出するときは防寒具をしっかり身につけることが大切です。
室内では暖房等を使用し寒くならないようにする必要がありますが、トイレやお風呂は見落とされがちですので注意しましょう。
まとめ
高血圧は自覚症状が少ない一方で、放置すると大きな病気を引き起こすリスクの高い状態です。
発症・進行には食事を中心とした生活習慣が大きく関係しており、これらの見直しが治療においても重要なポイントとなります。
具体的には、高血圧のリスクとなる肥満を改善し、食塩およびアルコールの摂取を減らすこと、カリウム、カルシウム、食物繊維、不飽和脂肪酸を積極的にとることが大切です。
野菜、果物、きのこ、海藻、低脂肪の乳製品を意識して取り入れるようにしましょう。
減塩調味料やノンアルコール飲料、植物油等も減らしたいものと置き換えて使うと食事改善に効果的です。
運動、禁煙などの生活習慣の改善と合わせて早めに取り組みたいですね。
参考文献
Keiko Asakura, Ken Uechi, Yuki Sasaki, Shizuko Masayasu and Satoshi Sasaki. Estimation of sodium and potassium intakes assessed by two 24 h urine collections in healthy Japanese adults: a nationwide study British Journal of Nutrition Volume 112, Issue 7 14 October 2014 , pp. 1195-1205
厚生労働省:「日本人の食事摂取基準(2020年版)策定検討会」 報告書
五訂増補 調理のためのベーシックデータ. 女子栄養大学出版部, 2009.6
エスビー食品株式会社:「商品情報 マジックソルト オリジナル」
厚生労働省:「「健康づくりのための身体活動基準2013」及び「健康づくりのための身体活動指針(アクティブガイド)」について」
医学ボランティア会JCVN:「高血圧とは?原因と対策方法、合併症のリスクなどを解説」
記事監修

院長 内田 智之
- 日暮里・三河島内科クリニック 院長
- 日本内科学会総合内科専門医
- 日本血液学会血液専門医
- 日本血液学会血液指導医
- ICLSディレクター
- がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修修了
- 難病指定医

管理栄養士 土肥 加奈
2012年に管理栄養士資格を取得後、ドラッグストアに勤務し、登録販売者の資格も取得しました。
医薬品やサプリメント、栄養に関する包括的な健康相談に従事し、現在はクリニック専門のホームページディレクターとして活動しています。








