血圧が150,160,170,180,200を超えて大丈夫?
血圧とは
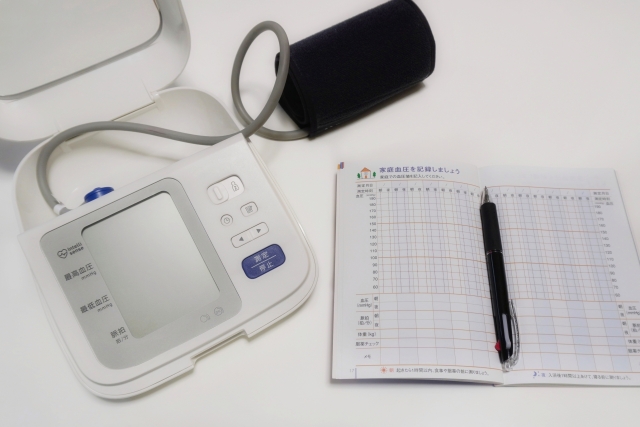 血圧とは、心臓が血液を全身に送り出すときに血管にかかる圧力のことです。血圧は「収縮期血圧(上の血圧)」と「拡張期血圧(下の血圧)」の2つで表され、正常値はおおむね上が120mmHg未満、下が80mmHg未満とされています。血圧が高い状態が続くと、動脈硬化が進行し、脳卒中や心筋梗塞などの重大な病気のリスクが高まります。高血圧の多くは自覚症状がないため、定期的な測定が大切です。食事の塩分を控える、適度な運動、ストレスの軽減、禁煙などの生活改善により、血圧のコントロールが期待できます。
血圧とは、心臓が血液を全身に送り出すときに血管にかかる圧力のことです。血圧は「収縮期血圧(上の血圧)」と「拡張期血圧(下の血圧)」の2つで表され、正常値はおおむね上が120mmHg未満、下が80mmHg未満とされています。血圧が高い状態が続くと、動脈硬化が進行し、脳卒中や心筋梗塞などの重大な病気のリスクが高まります。高血圧の多くは自覚症状がないため、定期的な測定が大切です。食事の塩分を控える、適度な運動、ストレスの軽減、禁煙などの生活改善により、血圧のコントロールが期待できます。
血圧の危険な数値(数字)はいくつ?
血圧の「危険な数値」は、収縮期(上の血圧)が180mmHg以上、または拡張期(下の血圧)が120mmHg以上の場合です。特に、頭痛・悪心・嘔吐・息苦しさ・視力障害・意識障害などの症状がある場合は「高血圧緊急症」の可能性があり、すぐに医療機関を受診すべき状態です。
「高血圧緊急症」とは、高度の血圧上昇によって、脳、心臓、大血管などの臓器に障害が生じ、直ちに降圧が必要な病態です。
血圧2回測ると数値が全然違う?
血圧は、同じ人でも測るたびに数値が変わることがあり、1回目と2回目で大きく違う場合も珍しくありません。これは、緊張や不安、測定姿勢、腕の位置などの影響によるものです。特に1回目は緊張や測定による刺激で高めに出やすく、2回目は落ち着いてやや低くなる傾向があります。また、連続して測ると腕の血流が変わり、値がばらつくこともあります。正確な血圧を知るには、1~2分間隔で2~3回測定し、その平均値を参考にするのが望ましいとされています。
水をたくさん飲むと血圧は下がる?
水をたくさん飲むことで血圧が大きく下がることは通常ありませんが、適度な水分補給は血圧の安定に役立ちます。体内の水分が不足すると血液の粘度が高くなり、血管の抵抗が増して血圧が上がることがあります。そのため、脱水を防ぐことで間接的に高血圧の予防につながる可能性があります。ただし、腎臓や心臓に持病がある人が過剰に水分をとると、むくみや心不全を招くおそれがあるため注意が必要です。水分補給は1日1.2~1.5リットルを目安に、こまめにとることが望ましいとされています。
血圧150超えのリスク
血圧が150mmHgを超える状態が続くと、高血圧症と診断される可能性が高くなり、さまざまな健康リスクが生じます。特に収縮期血圧(上の血圧)が150mmHg以上の場合、以下のような重大な病気のリスクが上昇します。
脳卒中(脳出血・脳梗塞)
高血圧は、脳の血管に強い圧力をかけ続けるため、破裂の原因になります。動脈硬化の進行により脳梗塞のリスクも高まります。
心筋梗塞・狭心症
血管の内側が傷つきやすくなり、動脈硬化が進行し血管が詰まりやすくなります。
心不全
心臓に負担がかかり続けると、ポンプ機能が低下し、息切れやむくみなどの症状が現れます。
腎機能障害(腎硬化症)
腎臓の血管にも影響が及び、慢性腎臓病や腎不全を招く恐れがあります。
認知症のリスク上昇
動脈硬化により脳の血流が悪くなることで、脳の機能が低下することがあります。中年期の高血圧症は高齢期の認知症の危険因子として知られています。
血圧160超えのリスク
血圧が160mmHgを超える状態が続くと、「高血圧(Ⅱ度)」に分類され、重大な病気のリスクが大幅に高まります。以下のような合併症が起こる可能性があります。
早めに生活習慣を見直すとともに、必要に応じて薬による治療を受けることが重要です。
脳卒中(脳出血・脳梗塞)
高血圧が続くと、脳の血管が破れやすくなり、動脈硬化の進行により詰まりやすくもなり、命に関わる脳卒中のリスクが上昇します。
心筋梗塞・狭心症
血管に負担がかかり、動脈硬化が進むことで心臓の血管が詰まりやすくなります。
心不全
心臓が血液を全身に送り出す力が弱くなり、息切れやむくみなどの症状が現れることがあります。
腎機能障害(腎硬化症)
腎臓の血管にも影響し、機能が低下して慢性腎臓病の原因や人工透析導入の要因になることがあります。
血圧170超えのリスク
血圧が170mmHgを超える状態は「高血圧(Ⅱ度)」またはそれ以上に該当し、命にかかわる重大な合併症のリスクが非常に高い危険な状態です。このような高血圧を放置すると、次のような健康被害が起こりやすくなります。
脳卒中(脳出血・脳梗塞)
高い血圧が続くと、脳の血管が破れやすくなりますし、動脈硬化の進展により血管が詰まりやすくもなっています。突然の意識障害や麻痺を引き起こす恐れがあります。
心筋梗塞・狭心症
心臓の血管(冠動脈)が詰まりやすくなります。胸の痛みや、それが進行すると心停止につながることがあります。
心不全
心臓への負担が大きくなり、息切れ、むくみ、疲労感などの症状が現れます。
腎機能障害(腎硬化症)
腎臓の血管が障害を受け、老廃物をうまく排出できなくなり、慢性腎臓病や透析が必要になることもあります。
高血圧緊急症
血圧が180/120mmHgに近づくと、「高血圧緊急症」になり、すぐに治療が必要な状態になることもあります。
血圧180超えのリスク
血圧が180mmHgを超える状態は、Ⅲ度高血圧です。Ⅳ度高血圧はなく、高血圧の分類で一番高い段階です。命にかかわる可能性が高い危険な状態です。特に上(収縮期血圧)180mmHg以上、または下(拡張期血圧)120mmHg以上の場合、ただちに医療機関での対応が必要です。
脳卒中(脳出血・脳梗塞)
非常に高い血圧が脳の血管を破裂させるリスクが急激に上昇します。
心不全
心臓に強い負担がかかることで心臓のポンプ機能が低下して息切れや下肢にむくみ(浮腫)が起こる可能性があります。
急性大動脈解離
高い血圧によって大動脈の壁が裂けてしまう可能性があります。背中に強い痛みを伴い、命に直結します。
腎機能障害(腎硬化症)
腎臓の血流が障害され、急激に腎機能が低下することがあります。
血圧200超えのリスク
血圧が200mmHgを超える状態は、非常に危険で緊急の医療対応が必要な状態です。このレベルの高血圧は、脳・心臓・血管などの重要な臓器に深刻なダメージを与える可能性が極めて高く、命にかかわるリスクがあります。
脳出血
血管が極端な圧力に耐えきれず破裂(脳出血)するリスクが極めて高まります。突然の意識障害、手足の麻痺、言語障害(構音障害や呂律障害)などを引き起こすこともあります。
心不全
心臓に過剰な負担がかかり、息切れや浮腫が生じ、突然死につながる恐れもあります。
急性大動脈解離
大動脈の壁が裂ける「大動脈解離」は、血圧が高ければ高いほど発症のリスクは高まります。
激しい胸や背中の痛みが特徴です。命を落とす危険性もあります。
高血圧性脳症
脳血流の自動調節能を超えた血圧になると、ひどい頭痛、悪心・嘔吐、けいれん、意識障害、視力障害などの症状が出ることもあります。
血圧は低ければ問題ない?
血圧が低いことは必ずしも問題ないとは限りません。一般的に、血圧が低すぎる状態は「低血圧」と呼ばれ、めまいや立ちくらみ、疲れやすさ、集中力の低下などの症状を引き起こすことがあります。特に、収縮期血圧が90mmHg以下の場合は注意が必要です。また、極端に低い血圧は脳や心臓への血流不足を招き、場合によっては失神やけいれんを引き起こすこともあります。ただし、元々血圧が低い人でも症状がなければ問題ないことも多いです。健康的な血圧を維持するためには、急激な血圧の変動を避け、バランスの取れた食事や適度な運動を心がけることが大切です。何か気になる症状があれば医師に相談しましょう。








