尿酸値を下げる食べ物を一覧で紹介!痛風予防の食事療法のポイントとは?
健康診断で尿酸値が高いと指摘された場合に、通風を予防するために尿酸値の改善を図るにはどのような食べ物や飲み物を選ぶべきなのでしょうか?
この記事では、尿酸値の改善に役立つ食べ物・飲み物を分かりやすく一覧でご紹介します。
さらに、尿酸値を下げるために押さえておきたい食事のポイントや、日常生活で見直すべき習慣についても詳しく解説します。
尿酸値が気になる方におすすめの食材を活用した簡単レシピも取り上げていますので、ぜひ参考にしてみてください。
尿酸とは?健康リスクと生活習慣との関係

尿酸は、体内でエネルギー源や細胞内の核酸成分であるプリン体が代謝される際に生じる老廃物の一種です。
血液中の尿酸が増えすぎると痛風を始めとした健康上のトラブルに繋がるため、適正範囲内に留める必要があります。
尿酸値とは?
尿酸値とは、血液中に含まれる尿酸の濃度を表す数値です。
尿酸は血中で最大7㎎/dlまで溶け込むことができるため、この値が正常範囲とされています。
しかし、体内で尿酸が過剰に生成されたり、排泄が滞ったりすることで尿酸値が上昇します。
尿酸値が7㎎/dlを超える場合、「高尿酸血症」と診断されます。
尿酸値が高くなるとどうなる?
尿酸値の高い状態を放置すると、血液中で溶けきれなくなった尿酸が尿酸塩結晶となります。
尿酸塩の結晶が関節やその他の組織に沈着することで、さまざまな健康問題を引き起こす可能性があります。
具体的には、痛風関節炎や痛風結節、さらには腎障害や尿路結石などのリスクが高まります。
特に、痛風関節炎と痛風結節は「痛風」と総称され、名前の由来は「風が吹くだけでも激痛を感じる」とされるほどの強い痛みを伴う点にあります。
尿酸値が高くなる原因
尿酸値が高くなる原因はさまざまですが、いずれも生活習慣が深く関係しています。
■尿酸値を挙げる要因
- 遺伝的要因
- 肥満
- 食べ過ぎ(特にプリン体、脂肪、たんぱく質、果糖を多く含む食事)
- 飲み過ぎ(アルコールの過剰摂取)
- 運動不足
- 過度な運動
- ストレスや睡眠不足
さらに、高尿酸血症や痛風を抱える場合には、高血圧、脂質異常症、糖尿病、慢性腎臓病などの他の生活習慣病や、動脈硬化性疾患のリスクが高まることが知られています。
そのため、尿酸値のコントロールは痛風発作の予防にとどまらず、生活習慣病や心血管疾患の予防にも重要です。早めの対策を心掛け、健康リスクを減らすことが大切です。
尿酸値を下げる食事療法のポイント

尿酸値が上がる原因の多くは、食事を含む生活習慣に深く関係しています。
実際、食事内容を見直すことで尿酸値が低下し、痛風の発症頻度が減少することが分かっています。
そのため、尿酸値が高い方にとって、食事改善は欠かせない取り組みといえるでしょう。
尿酸値を下げたり、痛風の予防や改善を目指したりするために意識したい栄養面でのポイントを詳しく解説します。
摂取カロリーを制限して肥満を改善
肥満である場合には食事からの摂取カロリーを制限し、適正体重を目指しましょう。
肥満、とりわけ内臓脂肪型肥満は尿酸値を上昇させる主な要因の一つとされており、肥満を解消することで尿酸値の低下や痛風発作の頻度軽減が期待できます。
そのため、まずは食事からの摂取カロリーを適正範囲に抑え、体重の減少と肥満解消を目指すことが重要です。
摂取エネルギーの目安は、身長をもとに計算される標準体重や日常の運動量に基づいて決まり、個人差があります。
また、急激な体重減少は尿酸値を逆に上昇させる恐れがあるため、ゆっくりとしたペースでの減量が推奨されています。
適切な摂取カロリーや体重減少目標は、個々の体質や生活状況によって異なるため、具体的な数値や目標設定については、医師や管理栄養士と相談することが望ましいでしょう。
無理のないペースでのダイエットを心掛けながら、健康的な体重を目指していくことが大切です。
プリン体を制限する
食事由来のプリン体摂取量を制限しましょう。
食品に含まれるプリン体は体内で分解される過程で尿酸を生成し、尿酸値を上昇させるため、摂取量を適正範囲に抑える必要があります。
高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン第3版では、1日あたりのプリン体摂取量を400㎎以下に制限することが推奨されています。
■プリン体の摂取量を抑える方法
- プリン体を多く含む食品を避ける、量や頻度を控える
- 茹でる、煮るなどプリン体を減らす調理法を行う
プリン体の多い食品を控えるだけでなく、調理方法や食べ方を工夫して、無理なく尿酸値の管理を目指しましょう。
アルコールを制限する
アルコールを含む酒類の摂取を控えましょう。
アルコールは肝臓で分解される過程で体内のプリン体を利用し尿酸を生成するため、飲酒量が多いと尿酸値を上昇させる原因となることが知られています。
また、アルコール摂取量が増えるほど痛風発症リスクも高まるため、適正範囲を守るだけでなく、必要に応じてさらに控えることが推奨されます。
■尿酸値管理のための飲酒のポイント
- アルコールの摂取量を適正範囲内(1日あたりアルコール20g以下)に抑える
- プリン体が少ない蒸留酒(焼酎やウイスキーなど)を選ぶ
特にビールや発泡酒など一部のお酒はアルコールに加えてプリン体を多く含むため、飲む量や種類の選択に注意が必要です。
ビール1缶(350ml)には約10~20㎎のプリン体が含まれることが多く、他のお酒と比較して影響が大きくなる場合があります。
水分を十分に摂取する
尿酸値を適切に抑えるためには、体内で尿酸の排泄を促すため、十分な水分摂取を心がけましょう。
高尿酸血症の方は尿路結石を発症しやすいことが知られており、これを予防するためにも、1日あたりの尿量が2リットル以上になるよう水分をしっかり補給することが推奨されています。
■水分補給のポイント
- カフェインや糖分を含まない水やお茶を中心に選ぶ
- こまめに水分を摂取し、1度に大量に飲むのではなく、1日の中で均等に摂るよう心掛ける
ただし、腎臓機能に問題がある場合は、1日の水分摂取量に制限が設けられることがあります。
この場合、医師の指導を受けたうえで適切な摂取量を守ることが大切です。
不安な場合は医師や専門家に相談し、自身の健康状態に合った水分補給を心掛けてください。
ビタミンCを摂取する
ビタミンCを含む食品を意識して取り入れるようにしましょう。
ビタミンCは、尿酸値を下げる効果があることが知られており、ビタミンCを豊富に含む食品を積極的に摂取することが尿酸値の改善に役立つと考えられます。
ビタミンCを多く含む代表的な食品である果物や野菜を日常の食事にバランスよく取り入れることをおすすめします。
ただし、ビタミンCの過剰摂取には注意が必要です。特にサプリメントを使用して必要以上に摂取すると、尿路結石の発症や再発のリスクが増加する可能性があります。
そのため、ビタミンCを補給する際には、食品を主な摂取源とし、サプリメントを利用する場合は適量を守るよう心掛けましょう。
尿をアルカリ化する食品を摂取する
尿をアルカリ化する食品を摂取することも大切です。
尿酸は酸性環境で結晶化しやすく、この状態が尿路結石の発生リスクを高めるとされています。
したがって、尿酸値を直接下げることだけでなく、高尿酸血症に合併しやすい尿路結石の予防として、尿をアルカリ性に近づけることが効果的であると報告されています。
尿をアルカリ化するには、クエン酸などの「有機酸」を多く含む食材を積極的に摂取することが推奨されています。
■有機酸を含む食品の具体例
- レモンやオレンジなどの柑橘類
- 梅干し
- 酢を使った料理など
さらに、「DASH食」と呼ばれる食事スタイルに近い食事内容を実践することで、尿のアルカリ度が高まる傾向があることも知られています。
この食事法は、尿酸値の改善だけでなく、全体的な健康維持にも役立つと言われています。
DASH食、地中海食、果物・大豆食を取り入れる
尿酸値の低下に効果が期待できる食事モデルとして、「DASH食」「地中海食」「果物・大豆食」を取り入れてみましょう。
- DASH食
果物、野菜、低脂肪の牛乳や乳製品の摂取を増やし、脂肪分や飽和脂肪酸、コレステロールの摂取を抑えた食事内容 - 地中海食
オリーブオイルなどの植物油、豆類、ナッツ、果物、魚介類を多く摂取し、赤肉や高脂肪食品、焼き菓子、スナック類の摂取を控える食事スタイル - 果物・大豆食
果物と大豆製品を豊富に摂取する食事内容
これらの食事モデルはいずれも、野菜や果物の摂取量を増やし、肉類や脂肪分の摂取量を減らす内容となっています。
そのため、以下の尿酸値改善に役立つポイント(肥満解消のための摂取カロリーの適正化、プリン体の摂取制限、ビタミンCの摂取増加、尿をアルカリ化する食品の摂取)を満たしやすい特徴を持っています。
尿酸値を下げるための理想的な食事をイメージしやすくする参考モデルとして、これらの特徴を頭に入れておくと便利です。
尿酸値を下げる食べ物・飲み物一覧
食品に含まれる成分には、尿酸値の上昇に作用する物がある一方で、尿酸値を下げる作用を持つものもあります。
そのため、日常的にどのような食べ物や飲み物を選ぶかが、尿酸値のコントロールや痛風の予防において重要なポイントとなります。
ここからは、尿酸値を下げるのに役立つ食べ物や飲み物を具体例を交えて一覧で紹介します。
肥満予防の為の配慮は必要ですが、適正なカロリー範囲内でこれらを上手に取り入れることで、尿酸値の改善や痛風の発症予防につながります。ぜひ、日々の食生活に役立ててみてください。
野菜

野菜類は、重さあたりのカロリーが低く、食事の満足感を保ちながら摂取カロリーを抑えられるため、高尿酸血症のリスク要因である肥満の解消を目指す際に非常に役立つ食品です。
さらに、野菜は尿酸値の低下に寄与するとされるビタミンCや、腸内環境を整える食物繊維を豊富に含んでいます。また、水分を多く含むため、体内の水分補給にも一役買います。
■ビタミンCを多く含む野菜類
| 食品名 | 100gあたりのビタミンC含有量 |
|---|---|
| パプリカ(赤) | 170mg |
| 芽キャベツ | 160mg |
| パプリカ(オレンジ) | 150mg |
| パプリカ(黃) | 150mg |
| ブロッコリー | 130mg |
これらの野菜はビタミンCの優れた供給源ですが、特定の野菜にこだわり過ぎず、さまざまな種類の野菜を取り入れることが大切です。
野菜全般を意識して食事に組み込むことで、栄養バランスが整い、健康効果をより広範に得られます。
健康維持のためには、1日あたり350gの野菜を摂ることが推奨されています。この目安を達成するには、1日3食それぞれに野菜料理を1品以上加えることを心掛けるとよいでしょう。
サラダ、煮物、蒸し野菜、スープなど、調理法を工夫してバリエーションを増やすことで、飽きずに野菜を摂り続けることができます。
海藻

海藻類は低カロリーで、野菜類と同様に食物繊維の摂取源となる食品です。
■取り入れやすい海藻類の例
- わかめ(乾燥のもの)
- ひじき(乾燥のもの)
- めかぶ(味付け済みのもの)
- もずく(味付け済みのもの)
これらの海藻類は、食事のボリュームを保ちながらカロリーを抑えられるため、野菜と同じ感覚で積極的に取り入れるのがおすすめです。
味付け済みの製品や乾燥タイプの海藻は手軽に使えるため、忙しいときの食事準備にも役立ちます。
サラダやスープに加えたり、主菜の副菜として取り入れるなど、さまざまな方法で楽しむことができます。
ただし、海藻類の中でも海苔は他の種類に比べてプリン体を多く含むことが知られています。そのため、特にプリン体摂取を制限している場合には、海苔の摂取量に注意しましょう。
果物

果物は、ビタミンCや食物繊維を豊富に含む食品であり、また、水分が多いことから水分補給にも役立ちます。
さらに、尿をアルカリ化する効果が期待されるクエン酸や他の有機酸を含んでおり、尿酸値を下げる特徴を持つ食材として注目されています。
■ビタミンCを多く含む果物類
| 食品名 | 100gあたりのビタミンC含有量 |
|---|---|
| キウイフルーツ(黃) | 140mg |
| キウイフルーツ(緑) | 71mg |
| 柿 | 70mg |
| いちご | 62mg |
| ネーブルオレンジ | 60mg |
実際、果物を多く取り入れた食事モデルが尿酸値の低下に寄与することが報告されています。
リンゴやみかん、バナナなどの果物は手軽に食べられるだけでなく、自然な甘みがあるため、お菓子や高カロリーのスイーツの代わりに取り入れることで、摂取カロリーを抑える効果も期待できます。
ただし、果物の中には果糖を多く含むものもあります。果糖は過剰に摂取すると尿酸値を上昇させる可能性があるため、果物であれば無制限に食べてよいわけではありません。
一日の適切な摂取量を守ることが大切です。目安として、果物の摂取量は1日200g程度を意識するとよいでしょう。
低脂肪の牛乳や乳製品
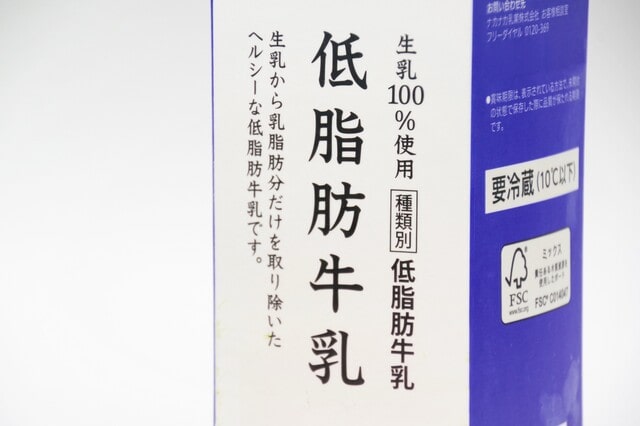
低脂肪の牛乳や乳製品を食事に取り入れてみましょう。
乳製品の中でも、特に低脂肪の乳製品は痛風の発症リスクを低減する効果があることが報告されています。
■低脂肪の乳製品の例
- 低脂肪牛乳
- 低脂肪ヨーグルト
- 低脂肪のチーズ(カッテージチーズなど)
一方で、バターや生クリームのような脂肪分の多い乳製品は、尿酸値を下げるために控えるべき飽和脂肪酸を多く含むため、摂取量に注意が必要です。
また、一部の市販ヨーグルトには、尿酸値の上昇を抑える効果が期待される乳酸菌を使用したものもあります。
これらの製品は機能性表示食品として販売されており、効果に関する研究結果が表示されています。
ただし、機能性表示食品は消費者庁の個別認可を受けたものではなく、治療や予防を目的としたものではない点を理解して選ぶことが重要です。
あくまで選択肢のひとつとして、日常の食生活に無理なく取り入れるとよいでしょう。
水、炭酸水、お茶

尿酸の排泄を促進し、尿路結石を予防するために、十分な水分摂取を意識しましょう。
人の体は1日あたり約2.5リットルの水分を必要とするとされ、そのうち1.6リットル程度が尿や便として排出されます。
尿酸値が高い場合は、1日あたり約2リットルの尿量を確保することが推奨されており、通常より多めの水分補給を心掛けることが求められます。
具体的な水分摂取量は、食事内容や活動量など個々の生活スタイルによって異なりますが、飲み水として1日2リットルを目安にするとよいでしょう。特に水や無糖の飲み物がおすすめです。
また、入浴中や睡眠中は汗をかくことで体内の水分が失われやすいため、入浴後や起床時に意識してコップ1杯(約200ml)の水を飲む習慣をつけると、体内の水分バランスを保ちやすくなります。
水分補給は、食事中や活動後にもこまめに行うのが理想です。体に負担をかけず、効率的に尿酸値の管理や健康維持を目指しましょう。
ゼロカロリー・ノンアルコールの飲み物

飲み物はゼロカロリー・ノンアルコールの物を選ぶようにしましょう。
アルコールの過剰摂取は尿酸値を上げる大きな要因のひとつとされています。
そのため、アルコールを控える方法としてノンアルコール飲料を取り入れることは、尿酸値の改善に役立つ有効な選択肢です。
近年ではビール風、カクテル風、日本酒風、梅酒風など、多様なノンアルコール飲料が販売されています。
これらはアルコール摂取を控えたい方に適した代替品として人気があります。
特に、ゼロカロリーや低プリン体のノンアルコール飲料を選ぶことで、余分なカロリーやプリン体の摂取を避けることができるため、尿酸値を下げるうえで理想的です。
ただし、商品によっては果糖や糖類が多く含まれるものもあるため、成分表示を確認し、糖質を控えた商品を選ぶよう心がけましょう。
アルコールを控えるだけでなく、甘いソフトドリンクをゼロカロリーのものに切り替えるのも有効な方法です。
ゼロカロリーのソフトドリンクは飲料由来のカロリーや糖分をカットできるのが特長です。
■ゼロカロリーの飲み物の例
- 無糖の炭酸水
- ゼロカロリーの清涼飲料水
- 無糖のお茶(緑茶、麦茶、烏龍茶など)
- 無糖のコーヒー
特に、果糖ブドウ糖液糖などの糖類を多く含む甘いソフトドリンクは尿酸値を上げる要因となるため、これらのゼロカロリー飲料に置き換えることで、糖分摂取を抑えつつ、日常の飲み物を健康的な選択に変えることができます。
アルコールや甘い飲料をゼロカロリー飲料に切り替え、適切な飲み方を心がけることで、尿酸値の改善や痛風リスクの軽減を効果的に進めることが可能です。
コーヒー

適量のコーヒーも取り入れるメリットがある飲み物の一つです。
コーヒーは尿酸値の低下に直接的な影響があるかは明確ではないものの、痛風の発症リスクを抑える効果が報告されています。
ただし、コーヒーにはカフェインが含まれており、過剰摂取すると不眠や血圧上昇などの体調不良を引き起こす可能性があります。
そのため、1日あたりマグカップ3杯程度を目安に摂取することで、カフェインの摂りすぎを防ぎながら健康的に楽しむことができます。
なお、ブラックコーヒーを選ぶことで余分な糖分やカロリーを控えられ、摂取カロリーを気にする方にも適しています。
尿酸値が高い方におすすめのレシピ
尿酸値が高い方でも安心して食べられるレシピを紹介します。
ノンアルコールの飲み物と合わせて晩酌気分を楽しめるメニューです。
毎日の食事作りのヒントにしてくださいね。
低プリン体食材で作るキムチチーズチヂミ
材料(2人分)
-
小麦粉 100g
-
片栗粉 60g
-
顆粒中華だし小さじ1(2.5g)
-
卵 1個(50g)
-
水 100ml
-
ニラ…1/2束(50g)
-
キムチ…100g
-
モッツアレラチーズ…50g
-
ごま油…大さじ1(12g)
-
醤油…大さじ1(15g)
-
砂糖…小さじ1(4g)
-
白いりごま…小さじ1(3g)
作り方
- ニラは5cmの長さに切る。キムチは荒く刻む。
- ボウルに小麦粉、片栗粉、顆粒中華だしを加えて泡だて器でさっと混ぜる。
- 卵と水を加えてダマにならないように混ぜ、ニラ、キムチを加えて混ぜる。
- 熱したフライパンにごま油の半量をひき、生地を流し入れ、モッツアレラチーズをちぎって全体に乗せる。
- 裏面に香ばしく焼き目がついたらひっくり返し、フライパンのフチから残りのごま油を加える。
- 両面が焼けたら取り出し、食べやすい大きさに切る。
- タレの材料(醤油、砂糖、いりごま)をすべて混ぜて添える。
栄養価とコメント
- カロリー…475kcal
- たんぱく質…14.4g
- 脂質…15.3g
- 炭水化物…70.5g
- 食塩相当量…3.3g
- プリン体…30mg程度
プリン体の少ない食材を活用したおつまみメニューです。
満足感のある味わいながら、痛風の方でも安心して食べられる内容になっています。
ゼロカロリー・ノンアルコールの飲み物を合わせて、ヘルシーにお酒気分を味わってくださいね。
市販の低脂質タイプのチーズを活用すると更に脂質・カロリーを減らせます。
レシピは2人分ですが、他のメニューがあるときは1人分の量を減らすとカロリーのとりすぎを防げます。
尿酸値を上げる避けたほうが良い食べ物・飲み物

尿酸値が上がる原因には食事を含む生活習慣が深く関係しており、尿酸値を下げるためには尿酸値を上げる要因となる食事にも注意する必要があります。
プリン体やアルコール、果糖を多く含んだり、尿を酸化させることが知られている食品は尿酸値を上げることに繋がります。
尿酸値改善のために控えるべき食べ物・飲み物を紹介します。
プリン体を多く含む食品
プリン体は尿酸の元となる成分であり、摂取量が過剰になると尿酸値が上昇する原因となります。
そのため、高尿酸血症や痛風を予防・改善するためには、プリン体の摂取量を適切に管理することが重要です。
高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン(第3版) では、1日あたりのプリン体摂取量を 400mg以下 に抑えることが推奨されています。
■プリン体の多い食品の例
- レバー(鶏、豚、牛)
- 小魚(ちりめんじゃこ、煮干し、しらす干し、干しエビなど)
- 魚介類(カツオ、イワシ、イワシ干物、アジ干物など)
- 白子、あん肝
- 納豆
- 一部のサプリメント(ビール酵母、クロレラ、スピルリナ、DHA・RNAなど)
このうち、レバーや魚介類、納豆などは100gあたりのプリン体含有量が特別に高いわけではありませんが、1回の摂取量が多くなりやすいため、摂取量に注意しましょう。
反対に、魚介の乾物(ちりめんじゃこ、干しえびなど)や一部のサプリメント(ビール酵母など)は、重さあたりのプリン体含有量が非常に高く、少量でも摂取量に大きく影響します。
調理法でプリン体を減らすことも可能です。肉や魚介類は、スライスした後に湯通しすることでプリン体を溶け出させ、摂取量を減らすことが可能です。
煮る・茹でるといった調理法を取り入れてプリン体量をコントロールしましょう。
アルコールを含む酒類
アルコールの過剰摂取は尿酸値を上昇させる要因のひとつであり、高尿酸血症や痛風のリスクを高めるため、適量を守ることが重要です。
■尿酸値への影響を最小限に抑えるためのアルコール摂取量(上限)の目安
- 日本酒 1合(180ml)
- ビール 350~500ml(製品ごとのアルコール度数やプリン体含有量による)
- ウイスキー 60ml(ダブル1杯)
- ワイン 148ml(約1杯強)
アルコールの影響を軽減するためのポイントとして、週2日の休肝日を設けることも大切です。
連日の飲酒は肝臓に負担をかけるだけでなく、尿酸の排出を妨げる要因になります。週に2日程度、アルコールを控える日を作ることで、尿酸値への影響を抑えることが期待できます。
また、ビールなど一部のアルコール飲料にはプリン体が多く含まれているため、尿酸値を管理するためには、プリン体ゼロのビールや焼酎、ウイスキーなどを選ぶのも一つの方法です。
アルコールは適量であれば楽しめますが、過剰な摂取は尿酸値の上昇だけでなく、肥満や高血圧、脂肪肝などのリスクも高めます。日々の飲酒量を意識しながら、健康的な飲み方を心がけましょう。
尿を酸化させる食品
尿酸が結晶化しやすくなるのを防ぐため、尿を過度に酸性に傾ける食事は控えることが推奨されています。
尿が酸性に傾きやすい具体的な食品が特定されているわけではありませんが、以下のような食習慣によって尿pHが酸性に傾くことが報告されています。
- たんぱく質や動物性食品(肉類、魚介類、卵、乳製品)の過剰摂取
- 絶食や極端な食事制限
尿を過度に酸性にしないためには、バランスの取れた食事が重要であり、食事は単に制限するのではなく、栄養バランスを整えながら無理なく継続できる方法を取り入れることが大切です。
果糖を含むジュース類
果糖を含むジュース類は控えめにすることを意識しましょう。
果糖は糖質の一種で、砂糖や果糖ブドウ糖液糖(ガムシロップ) などに多く含まれる成分です。
特に、加工食品や清涼飲料水、ジュース類に多く使用されており、日常的に摂取する機会が多い糖類のひとつです。
■果糖を多く含むジュース類の例
- 清涼飲料水(炭酸飲料・スポーツドリンク・エナジードリンク)
- 果汁100%ジュース・フルーツ加工飲料
このほか、砂糖や果糖ブドウ糖液糖を使用した菓子・アイスクリームも果糖を多く含んでいます。
これらの食品・飲料の摂取によって、尿酸値の上昇が促されることが報告されています。特に、清涼飲料水やジュース類は手軽に大量に飲めてしまうため、無意識のうちに過剰摂取しやすい点にも注意が必要です。
水分補給は尿酸の排出に重要ですが、果糖の摂取量が多くならないよう適切な飲み物を選ぶようにしましょう。
尿酸値を下げるための生活習慣とは

高尿酸血症・痛風は生活習慣病のひとつであり、その発症や進行には食事だけでなく、日々の生活習慣も大きく関係しています。尿酸値をコントロールするためには、ライフスタイル全体を見直し、改善することが重要です。
ここでは、尿酸値の改善と痛風予防に役立つ生活習慣のポイントを紹介します。
これらを意識して取り入れることで、尿酸値の管理だけでなく、その他の生活習慣病の予防や健康維持にもつながりますので、ぜひ心がけてみてくださいね。
適度な運動を習慣にする
尿酸値が上がる主な原因のひとつである「肥満の解消」には、適度な運動が効果的です。
運動によって 消費カロリーを増やし、体脂肪を減少させる ことで、尿酸値の低下が期待できます。
ただし、極端に激しい運動や強い負荷のかかる筋トレは、体内のエネルギー代謝の影響で尿酸値を一時的に上昇させてしまうことがあるため、運動内容には注意が必要です。
■尿酸値の管理に適した運動のポイント
- 適度な負荷で無理なく行う(激しい運動は控える)
- 有酸素運動を中心にする(脂肪燃焼効果が期待できる)
- こまめに水分補給を行い、脱水を防ぐ
具体的な運動内容としては、以下のような脈が少し速くなる程度の軽い運動が推奨されています。
- ウォーキング
- スロージョギング(負荷をかけすぎない軽いランニング)
- サイクリング
- 社交ダンス
このような運動を1回10分以上、1日合計30分~60分程度 行うことが望ましいとされています。
まとまった時間を確保するのが難しい場合には、日常生活の中で少しでも体を動かす習慣を増やす ことが大切です。
- エレベーターではなく階段を使う
- 通勤時に1駅分歩く
- 家事の合間に軽いストレッチを取り入れる
こうした 「ちょこっと運動」 を積み重ねることで、無理なく体を動かす時間を増やし、尿酸値のコントロールにつなげていきましょう。
ストレスをためないようにする
ストレスや睡眠不足も高尿酸血症の要因の一つとされており、これらは肥満やその他の生活習慣病とも深く関係しています。
尿酸値の管理だけでなく、健康維持のためにも十分な休養を確保することが大切です。
- 毎日の睡眠時間を十分に確保するため、就寝時間を早める
- リラックスできる時間を意識的につくり、ストレスをため込まない
- 趣味や適度な運動を取り入れ、気分転換を心掛ける
このような生活習慣の改善を継続することで、尿酸値の上昇を防ぎながら、より健康的なライフスタイルを実現できるでしょう。
まとめ
高尿酸血症や痛風が起こる原因には、肥満や食事内容の問題が大きく関係しています。
尿酸値を下げるためには食事の見直しを行って肥満の解消やプリン体、アルコール、果糖等の摂取量を減らすようにしましょう。
具体的には、バランスの取れた食事を摂ることを前提に、野菜、海藻、果物、低脂肪の乳製品を積極的に取り入れましょう。
ノンアルコール飲料やゼロカロリー飲料を上手に取り入れることで、食事制限の負担を減らすことにも役立ちます。
過度の食事制限は逆効果になることもありますので、長期的に取り組むことを意識しましょう。
また、運動など生活習慣の見直しも有効です。
食事及び生活習慣の具体的な改善ポイントは医師や管理栄養士など、専門家のアドバイスをうけるようにしましょう。
参考文献
日本痛風・核酸代謝学会ガイドライン改訂委員会:「高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン 第3版・2022年追補版」
栗原 久.日常生活の中におけるカフェイン摂取-作用機序と安全性評価-,東京福祉大学・大学院紀要 第6巻 第2号(Bulletin of Tokyo University and Graduate School of Social Welfare) pp109-125 (2016,3)
日本痛風・核酸代謝学会ガイドライン改訂委員会:「高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン 第2版(旧版)」
金子 希代子, 福内 友子, 稲沢 克紀, 山岡 法子, 藤森 新, 食品中プリン体含量および塩基別含有率の比較, 痛風と核酸代謝, 2015, 39 巻, 1 号, p. 7-21
記事監修

院長 内田 智之
- 日暮里・三河島内科クリニック 院長
- 日本内科学会総合内科専門医
- 日本血液学会血液専門医
- 日本血液学会血液指導医
- ICLSディレクター
- がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修修了
- 難病指定医

管理栄養士 土肥 加奈
2012年に管理栄養士資格を取得後、ドラッグストアに勤務し、登録販売者の資格も取得しました。
医薬品やサプリメント、栄養に関する包括的な健康相談に従事し、現在はクリニック専門のホームページディレクターとして活動しています。








