脂質異常症で食べてはいけないもの一覧。改善のための食事療法のポイントを紹介
脂質異常症(高脂血症)は糖尿病、高血圧と並ぶ生活習慣病のひとつであり、食事が深く関係している病気です。
また、脂質異常症にはいくつかの種類があり、それぞれ避けるべき食べ物・積極的にとるべき食べ物が異なります。
この記事では、脂質異常症と診断された方向けに、毎日の食事で注意が必要な食べ物・飲み物の具体例を紹介します。
脂質異常症の診断基準、基本的な治療方法、積極的に食べたい食べ物の例や外食・コンビニでの注意点、おすすめレシピも紹介していますので、ぜひ参考にしてくださいね。
脂質異常症とは
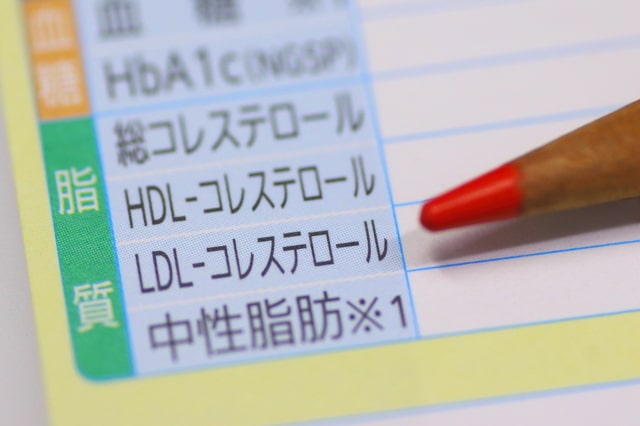
脂質異常症とは、体内の脂質代謝に異常が生じ、血中の脂質が基準となる範囲から外れた状態のことを指します。
2007年より以前は「高脂血症」と呼ばれていましたが、血中脂質が高いことだけではないことから、「脂質異常症」に名称が変わりました。
脂質異常症にはいくつかの種類があり、いずれも生活習慣上の問題点が原因となります。また、放置すると大きな病気につながる点も共通しています。
脂質異常症の種類と放置した時のリスク、原因となるものについて解説します。
脂質異常症の種類
脂質異常症は血中脂質の種類によって4つに分けられます。
- 高LDLコレステロール血症
- 低HDLコレステロール血症
- 高トリグリセライド血症
- 高non-HDLコレステロール血症
それぞれのコレステロールが多いこと・少ないことによる影響を解説します。
高LDLコレステロール血症
LDLコレステロールはいわゆる「悪玉コレステロール」で、肝臓から全身へコレステロールを運んでいますが、増えすぎると血管内にコレステロールを沈着させて血管を狭くしてしまいます。
低HDLコレステロール血症
一方、HDLコレステロールはいわゆる「善玉コレステロール」で、全身から余分なコレステロールを改修して肝臓に運んでいますが、少なすぎるとコレステロールが血管内に溜まりやすくなります。
高トリグリセライド血症
トリグリセライドは「中性脂肪」とも言い、体内では体脂肪の主成分となっていますが、血液中に増えすぎると血管内にコレステロールが溜まりやすくなってしまいます。(高トリグリセライド血症)
高non-HDLコレステロール血症
non-HDLコレステロールとは、「HDLコレステロール以外のコレステロール」のことで、LDLコレステロールに加えてVLDLコレステロールやIDLコレステロールなどが含まれます。
LDLと同様に、増えすぎると血管内にコレステロールを沈着させて血管を狭くしてしまいます。(高non-HDLコレステロール血症)
脂質異常症の診断基準
脂質異常症の診断は血液検査で行われます。
血液検査による脂質代謝の検査は一般的な健康診断の項目にもなっており、比較的身近な検査といえます。
血中脂質の量は食事摂取の影響を受けることが知られています。
そのため、脂質異常症の診断には10時間以上絶食した「空腹時」の血中脂質の濃度を使用します。
■脂質異常症の診断基準値
| 項目 | 診断基準値 | 診断名 |
|---|---|---|
| LDLコレステロール | 140mg/dL以上 | 高LDLコレステロール血症 |
| 120~139mg/dL | 境界域高LDLコレステロール血症 | |
| HDLコレステロール | 40mg/dL未満 | 低HDLコレステロール血症 |
| トリグリセライド(中性脂肪、TG) | 150mg/dL以上(空腹時採血) | 高トリグリセライド血症 |
| Non-HDLコレステロール | 170mg/dL以上 | 高non-HDLコレステロール血症 |
| 150~169mg/dL | 境界域高non-HDLコレステロール血症 |
日本動脈硬化学会:「動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版」より作成
「境界域」の場合は数値以外の高リスクな状態の有無によって治療の必要性が決まります。
脂質異常症を放置するリスク
脂質異常症は放っておくと血管を傷つけて「動脈硬化」を進行させ、動脈硬化性疾患を起こす原因になります。
動脈硬化とは血管の弾力性が失われて硬く・脆くなった状態のことを指します。
動脈硬化が進行すると、血管の内側(血管壁)にコレステロールが沈着してできる「プラーク」により血液の流れを妨げたり、血栓ができて血管が詰まるなどのトラブルにより、狭心症や心筋梗塞、脳梗塞といった大きな病気につながりやすい状態です。
また、脳の細い血管で動脈硬化が進行すると、血管が破裂して脳出血の原因となります。
このほか、動脈硬化が手足の血管で進行すると、手足のしびれや痛みの症状、潰瘍や壊死を起こすことも。
脂質異常症の段階では自覚症状はありませんが、放置せず原因の改善と進行予防に取り組むことが大切です。
また、脂質異常症と同じ生活習慣病である糖尿病、高血圧がある場合にはさらにリスクが高い状態となるため、早期に取り組むことが必要になります。
脂質異常症の原因
脂質異常症は生活習慣病のひとつであり、その原因には、以下のような生活習慣上の問題点が関係しています。
■脂質異常症の原因となる要素
| 疾患名 | リスク要因 |
|---|---|
| 高LDLコレステロール血症 | カロリーのとりすぎ・肥満 飽和脂肪酸のとりすぎ コレステロールのとりすぎ 遺伝素因 閉経後のホルモンバランスの変化 |
| 低HDLコレステロール血症 | カロリーのとりすぎ・肥満 血中トリグリセライド高値 遺伝素因 |
| 高トリグリセライド血症 | カロリーのとりすぎ・肥満 甘いもの、酒、糖質、油脂のとりすぎ 喫煙 運動不足 遺伝素因 |
脂質異常症とひとくくりにされがちですが、実はその原因は少しずつ異なっています。
自分が当てはまるものを把握し、それぞれに適した取り組みを行うことが大切です。
脂質異常症の治療方法

脂質異常症の治療は、食事療法と運動療法を基本とした「生活習慣の改善」が特に重要です。
食事療法と運動療法は薬による治療よりも優先度が高く、まず取り組むべきポイントといえます。
特に、肥満がある場合には生活習慣の改善による体重減少で脂質代謝異常全体の改善が期待できます。
短期間で急激に体重を落とすとリバウンドの恐れがあるため、緩やかに体重を減らすことが大切です。
望ましい生活習慣を身に着けることで適正な体重を目指すことを心がけましょう。
このほか、脂質異常症の種類ごとに適した食事内容や運動習慣を意識することで、脂質代謝の改善が期待できます。
個人の状態に適した食事療法や運動療法を行うためには、自己流ではなく医療機関に相談し、専門家の診療を受けることが大切です。
一般の内科のほか、循環器内科などを受診するようにしましょう。
脂質異常症の種類別食事療法のポイント

脂質異常症と診断されたら、食事のどのような点に気を付ければよいのでしょうか?
脂質異常症の改善のための食事療法では、脂質異常症全般に共通する内容と、種類ごとに異なる内容があります。
その理由は、上で紹介した脂質異常症の原因となるものが、種類ごとに異なるためです。
ここからは、脂質異常症にあてはまる方が共通して気をつけたいポイントと、脂質異常症の種類ごとにそれぞれ気をつけたいポイントをまとめて紹介します。
脂質異常症全般
脂質異常症全般に対して注意したいポイントは、「カロリーの取り過ぎを是正し、肥満を解消・予防すること」です。
カロリーのとりすぎ、またはそれによる肥満は脂質代謝の異常の原因となることから、脂質異常症全般に対する最大のリスク要因と言えます。
体重減少によって脂質の代謝も改善することが期待されます。
日本動脈硬化学会の動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版では、目標体重と日常生活での活動量からカロリー摂取量を定める方法が挙げられています。
■動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版における総カロリー摂取量の計算式
- カロリー摂取量(kcal/日)=目標体重(㎏)×身体活動量(以下から選択)
- 軽い労作…25~30
- 普通の労作…30~35
- 重い労作…35~
例えば、目標体重が70㎏で普通の労作を行っている人のカロリー摂取量の目安は、2100~2450kcal/日となります。
このとき、BMIが大きい人が厳しいカロリー制限によって急激に体重を減らすと、リバウンドを起こす可能性があります。
目標体重は自己判断で決めるのではなく、主治医等と相談しながら無理のないペースで減量できる数値を設定しましょう。
摂取カロリーを減らすためには、いくつかのポイントがあります。
- 高カロリーな食品を控える
- 低カロリーな食品を積極的にとる
- 食事量を少なめにする
脂質・糖質・たんぱく質が多い「高カロリーな食品」に偏った食生活では、同じ量でも摂取カロリーが過剰になりやすいといえます。
水分や食物繊維が多い「低カロリーな食品」を積極的にとり、食事のカロリー密度を下げるように取り組みましょう。
また、カロリー控えめな食事をとっていたとしても、食事量が多いと結果的にカロリーのとりすぎにつながります。
健康的な食事を適量範囲で食べることを意識しましょう。
高LDLコレステロール血症(悪玉コレステロールが多い方)
悪玉コレステロールが多い「高LDLコレステロール血症」の場合には、脂身の多い肉類や乳脂肪、加工食品を控え、魚や大豆製品、野菜・海藻・きのこ、玄米や全粒粉のような精製度の低い穀類を積極的に取り入れましょう。
血中のLDLコレステロールを上げる要因として、食品に含まれる飽和脂肪酸、コレステロール、トランス脂肪酸が挙げられます。
反対に多価不飽和脂肪酸、食物繊維の摂取量が増えるとLDLコレステロール値が下がることが知られています。
このほか、食事から摂取するカロリーのうち、脂質由来のカロリーの割合を適正範囲に下げることもLDLコレステロール値の低下につながるため、食事全体のバランスをとることも大切です。
■具体的なポイント
- 脂身の多い肉は避ける
- 肉の代わりに魚を取り入れる
- バターや生クリームは控えめにする
- バターの代わりに植物油を取り入れる
- 菓子パン、スナック菓子、インスタントラーメンは控えめにする
- たまごは食べすぎないようにする(1日1個程度ならOK)
- 野菜、海藻、きのこを積極的に食べる
- 精製度の低い穀類(玄米、全粒粉、押し麦、オートミールなど)を取り入れる
- カロリー計算アプリなどを活用し、脂質エネルギー比率を20~25%に抑える
高トリグリセライド血症(中性脂肪が多い方)
中性脂肪が高い「高トリグリセライド血症」の場合には、甘い飲み物やアルコールを控え、穀類や果物は適量を心がけましょう。
高トリグリセライド血症(中性脂肪が多い)は脂質異常症の中でも炭水化物(糖質)やアルコールのとりすぎが強く関係していることが知られています。
血中中性脂肪値を下げるためには、肥満の是正に加えて炭水化物のとりすぎを改善する必要があります。
また、魚の脂に含まれるn-3系脂肪酸は中性脂肪を下げる働きが知られています。
■具体的なポイント
- 甘い飲み物は控える
- お酒は適量範囲(純アルコールで20gまで)に抑え、休肝日を設ける
- 主食(ごはん、パン、麺など)は適量範囲に抑える
- 生の果物は適量範囲で、缶詰など加工品は控えめにする
- 魚を積極的にとる
低HDLコレステロール血症(善玉コレステロールが少ない方)
善玉コレステロールが少ない「低HDLコレステロール血症」では、食事療法の効果についてあまり明らかになってはいませんが、炭水化物由来カロリーの割合や、トランス脂肪酸の摂取が関連していると言われています。
また、HDLコレステロール値は高トリグリセライド血症と連動して上がることが多いため、糖質摂取を控えめにするような高トリグリセライド血症改善のための取り組みも有効とされています。
アルコールを摂取すると血中のHDLコレステロールが増えることが知られていますが、一方でアルコールは摂取カロリーの上乗せや各種臓器への負担を増やします。
HDLコレステロールを増やす目的で飲酒量を増やすメリットは少ないと考えましょう。
■具体的なポイント
- 菓子パン、スナック菓子、インスタントラーメンは控えめにする
- 甘い飲み物は控える
- 主食(ごはん、パン、麺など)は適量範囲に抑える
- 生の果物は適量範囲で、缶詰など甘い加工品は控えめにする
- 魚を積極的にとる
- お酒は適量範囲(純アルコールで20gまで)に抑え、休肝日を設ける
- お酒を増やす必要はない
脂質異常症で食べてはいけないもの一覧
脂質異常症は食事の影響を受けやすい疾患です。
ここからは、脂質異常症と診断されたときに、控えるべき食べ物・飲み物の具体例を紹介します。
ほんの少量でも絶対に食べてはいけないというものではありませんが、食べすぎないように食べる量や頻度を減らす必要がありますので、是非参考にしてくださいね。
高カロリーな食べ物

脂質異常症全般に対して、高カロリーな食べ物は控えめにすることを意識しましょう。
高カロリーな食品は摂取カロリーの過剰に繋がりやすく、肥満の改善と予防を妨げてしまいます。
- 揚げ物全般
- 脂身の多い肉(和牛肉、バラ肉、鶏皮など)
- 油脂類(バター、油全般)
- 砂糖の多いお菓子類
- 糖類を含むジュース類
- 酒類
これらの食品は重さあたりのカロリーが高かったり、必須栄養素が少ないために余分なカロリー摂取になりやすい食品です。
一度に食べる量や1週間のうちで食べる頻度を抑えることで、食事からの摂取カロリーを低く抑えることにも繋がります。
飽和脂肪酸の多い食べ物

高LDLコレステロール血症、低HDLコレステロール血症に対しては、飽和脂肪酸の多い食べ物は控えめにすることが効果的です。
飽和脂肪酸は肉の脂身や乳脂肪分のほか、一部の植物油に多く含まれています。
■飽和脂肪酸の主な摂取源となる食品の例
- 牛脂
- ラード
- 牛リブロース
- 豚バラ肉
- 鶏皮
- ベーコン
- バター
- 生クリーム
- クリームチーズ
- マーガリン
- ココナッツオイル
- チョコレート類
- スナック菓子
- 焼き菓子(クッキー、ケーキなど)
栄養バランスを整えつつ飽和脂肪酸の摂取量を減らすには、飽和脂肪酸の少ない食材と置き換えるのがおすすめです。肉類は魚や大豆製品に、バターなどの油脂は植物油に置き換えるのが良いでしょう。
高脂質の乳製品やお菓子などの嗜好品は食べる量や頻度を抑えるほか、低脂質低カロリーなものに置き換えるのも有効です。
コレステロールの多い食べ物

脂質異常症のうち、高LDLコレステロール血症の改善のためには、コレステロールの多い食べ物も控えめにしましょう。
コレステロールは動物性食品にのみ含まれる成分です。
■コレステロールの主な摂取源となる食品の例
- 鶏卵
- 煮干し(いわし)
- しらす
- すじこ、いくら
- レバー
- 数の子
- しらこ
- たらこ
これらの中でも、鶏卵は食べる頻度と量が多く、卵をよく食べる人ではコレステロールのとりすぎになりやすいと言えます。
動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2022 年版では、高LDLコレステロール血症においては1日あたりのコレステロール摂取量を200㎎未満に制限することが推奨されています。
一方、鶏卵1個約50gに含まれるコレステロール量は190㎎となっていますので、LDLコレステロールが高い人は1日に食べる卵は1個まで、その他のコレステロールが多い食品を食べる場合は卵は控えるといった調整ができるとよいでしょう。
糖質の多い食べ物

脂質異常症の中でも高トリグリセライド血症や低HDLコレステロール血症の改善には、糖質を多く含む食べ物は控えることを意識しましょう。
特に、以下のような砂糖を多く使った菓子類や嗜好飲料は必須栄養素が少なく余分なカロリー摂取になりやすい特徴があります。
- 菓子類
- 菓子パン
- ジュース類(ソフトドリンク、果物・野菜ジュース)
- スイーツ(ケーキ、アイス、プリンなど)
- フルーツ缶詰(シロップ漬け)
また、糖質はなるべく減らすのではなく、適量範囲でとることが大切です。
以下のような主食としてとる糖質は食べすぎないように注意し、適量摂取を心がけましょう。
- 米および米製品(米飯、餅など)
- 小麦製品(パン、麺など)
穀類は精製度の低いもの(玄米、全粒粉、もち麦、オートミール)などと置き換えて使うとより効果的です。
アルコールを含む飲み物

脂質異常症のうち、特に高トリグリセライド血症では、アルコールを含む酒類は適量を心がけましょう。
また、高トリグリセリド血症でない場合でも、アルコールのとりすぎはカロリーのとりすぎにつながること、高血圧、脂肪肝、膵炎といった脂質異常症以外の生活習慣病のリスクとなることから、適量範囲での飲酒に留めることが大切です。
動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版におけるアルコールの1日あたりの摂取量は25g以下(またはできるだけ控えること)が推奨されています。
アルコール25gに相当するお酒の量はアルコール度数によっても異なります。
市販の酒類ではパッケージにアルコール量が記載されていることも多いため、購入時や飲む際に確認することを意識しましょう。
このほか、脂質異常症のような動脈硬化性疾患だけに限らず、全体的な健康面を考慮した場合の「節度ある適度な飲酒」は1日あたり男性20g以下、女性10g以下となっています。
トランス脂肪酸の多い食べ物

高LDLコレステロール血症、低HDLコレステロールの場合には、飽和脂肪酸と合わせてトランス脂肪酸(工業的トランス脂肪酸)にも気を配れるとよいでしょう。
工業的トランス脂肪酸は飽和脂肪酸と同様、摂取量が血中のLDLコレステロールとHDLコレステロールに影響する成分です。
工業的に製造される油脂類やそれらを使用した加工食品に含まれています。
■トランス脂肪酸が含まれる食品の例
- マーガリン
- ショートニング
- 菓子類(クッキーなど)
- 菓子パン
トランス脂肪酸は飽和脂肪酸と比較すると同じ量でもLDLコレステロールを上げる作用が強い特徴がありますが、日本人の食生活では飽和脂肪酸と比較すると少ないため、LDLコレステロールに与える影響は飽和脂肪酸よりも小さいと考えられています。
脂質異常症の食事療法においてあまり優先度は高くありませんが、可能な範囲で気を配れると理想的です。
脂質異常症の改善に良い食べ物

脂質異常症で避けるべき食べ物とは反対に、積極的にとりたい、脂質異常症の改善によい食べ物も存在します。
ポイントは、普段の食事にプラスしてとるのではなく、脂質異常症で避けたい食べ物と置き換える形で取り入れること。
意識して取り入れたい食品の具体例を紹介します。
食物繊維の多い食べ物
食物繊維は食品に含まれる消化吸収されない成分で、穀類、野菜、果物、海藻、きのこなどの食品に多く含まれています。
食物繊維のうち、特に水溶性食物繊維は食事に含まれるコレステロールを排出して血中のLDLコレステロール値を下げるのに役立ちます。
また、水溶性食物繊維だけでなく、不溶性食物繊維を含む食物繊維の摂取量を増やすことは脂質異常症だけでなく生活習慣病全般の発症リスクを下げることが知られています。
そのため、水溶性・不溶性にかかわらず、以下のような食品を意識してとるのがおすすめです。
■食物繊維を豊富に含む食品
- 全粒穀物(玄米、全粒粉、押し麦、オートミール、そば粉など)
- 雑穀類(ヒエ、アワ、キヌア、アマランサスなど)
- 野菜類(全般)
- きのこ類(全般)
- 海藻類(全般)
このうち、全粒穀物や雑穀類はいつもの食事にプラスするとカロリーの上乗せになるので、普段の主食(白米、小麦製品)と置き換えて使うのがおすすめです。
野菜、きのこ、海藻類は重さあたりのカロリーが低く、食事のカサ増しに役立つのが魅力です。
1日350gを目標に積極的に食事に取り入れるようにしましょう。
多価不飽和脂肪酸の多い食べ物
多価不飽和脂肪酸は中性脂肪を構成する脂肪酸の一種で、血中のトリグリセライドやLDLコレステロールを低下させ、HDLコレステロールを増やす作用があります。
多価不飽和脂肪酸は植物油や魚類の脂肪分に比較的多く含まれています。
■多価不飽和脂肪酸を多く含む食品の例
- アマニ油
- ぶどう油(グレープシードオイル)
- 大豆油
- ごま油
- 米油
- キャノーラ油(菜種油)
- マグロのトロ
- サバ
- サンマ
- 鮭
- イワシ
一方で、多価不飽和脂肪酸は脂質の一種であり、取りすぎるとカロリーの過剰摂取につながります。
よって、普段の食事にプラスするのではなく、他の減らしたい食品、例えば飽和脂肪酸の多い肉類や乳脂肪と置き換えて使うのがおすすめです。
外食・コンビニで意識したいポイント
外食やコンビニ食は魅力的なメニューが多い一方で、健康面で望ましい食事内容にするのが難しい側面があります。
脂質異常症の改善のために、外食やコンビニで食事を選ぶ際に意識したいポイントをまとめました。
■外食やコンビニで食事を選ぶ際に意識したいポイント
- 和食を選ぶ
- どんぶりもの、一皿メニューを避けて多品目の定食メニューやお弁当を選ぶ
- 単品を組み合わせる場合は一汁三菜を意識する
- ご飯、おかずはともに大盛りにしない
- ご飯やパンの種類が選べる場合は雑穀米や全粒粉パンなどを選ぶ
- 野菜、きのこ、海藻たっぷりのおかずを追加する
- 揚げ物を避けて焼き、蒸し料理を選ぶ
- 肉より魚、大豆製品を選ぶ
- お菓子、デザートは控える(生の果物はOK)
- ジュースやお酒ではなく水やお茶を選ぶ
これらのポイントすべてに当てはまるようにする必要はありませんが、なるべく多くに当てはまるような食事内容にできるよう意識するようにしましょう。
はじめは気をつけるポイントが多く大変ですが、食事選びや組み合わせに慣れてくるとどのようなシチュエーションでも健康的な食事が取れるようになりますので、ぜひ挑戦してみてくださいね。
脂質異常症の方におすすめのレシピ2選を紹介
脂質異常症では食事面でのポイントが多くあります。
ここからは、脂質異常症の種類ごとのポイントを活かしたレシピを紹介します。
毎日の食事選び・食事作りの参考にしてくださいね。
高LDLコレステロール血症の方に。野菜たっぷりサバ缶のビビンバ
材料(1人分)
- もち麦ごはん(レトルト)…1パック(150g)
- サバ缶(味付き)…100g
- 焼き肉のたれ…大さじ1(18g)
- コチュジャン…小さじ1/3(2g)
- にんじん…30g
- もやし…30g
- 小松菜…30g
- ごま油…小さじ1(4g)
- 顆粒鶏ガラスープ…小さじ1(2.5g)
作り方
- にんじんは千切りに、小松菜は5㎝の長さに切る。
- にんじん、もやし、小松菜をそれぞれゆでて水けを絞り、合わせてごま油、鶏ガラスープで味付けする。
- サバ缶の身を取り出して焼き肉のタレとコチュジャンで和える。
- もち麦ごはんを商品表示に従ってレンジ加熱し、器に盛る。
- ごはんの上に野菜、サバを盛り付ける。
栄養価とコメント(1人分)
- カロリー…492kcal
- たんぱく質…27.8g
- 脂質…17.9g
- 炭水化物…58.4g
- 食物繊維…4.5g
- 食塩相当量…4.2g
- 飽和脂肪酸…4.03g
- 一価不飽和脂肪酸…5.53g
- 多価不飽和脂肪酸…5.36g
- コレステロール…95㎎
低カロリー・低脂質、肉より魚、動物性油脂より植物油、食物繊維を意識して摂りたい脂質異常症の方向けのレシピです。
がっつりメニューのビビンバですが、野菜たっぷり、お肉ではなくお魚を使い、栄養バランスを整えました。
普通のごはんではなくもち麦ごはんを活用して食物繊維もプラスしています。
どんぶりものですので、かき込まずゆっくりよく噛んで食べるよう意識しましょう!
高トリグリセライド血症の方に、砂糖不使用マンゴープリン
材料(作りやすい量:3個分)
- 冷凍マンゴー…120g
- 低脂肪乳…200g
- ラカントシロップ…大さじ1(18g)
- 粉ゼラチン…5g
- 水…30ml
作り方
- 冷凍マンゴーは自然解凍しておく。水を入れた器に粉ゼラチンを振り入れ、ふやかしておく。
- ミキサーまたはフードプロセッサーに解凍したマンゴー、低脂肪乳、ラカントシロップを加えて滑らかになるまで混ぜる。
- ふやかしたゼラチンを電子レンジ(600W)30秒加熱して溶かし、2に加えてよく混ぜる。
- 3を器に注ぎ、冷蔵庫で冷やし固める。
栄養価とコメント(1個分)
- カロリー…61kcal
- たんぱく質…4.2g
- 脂質…0.7g
- 炭水化物…11.7g
甘いものを控えたい高トリグリセライド血症でも安心して食べられるスイーツメニューです。
シロップ漬けの果物缶詰ではなく、砂糖を使っていない冷凍フルーツを活用しました。
低カロリー甘味料を使い、糖質とカロリーを抑えています。
脂質異常症改善のための食事以外のポイント

脂質異常症は食事の影響を大きく受けますが、食事以外の生活習慣も無関係ではありません。
特に重要なのが運動と禁煙で、脂質異常症だけでなくその他の生活習慣病全般、および健康全体に対してプラスの影響がありますので、少しずつでも取り組むことが大切です。
運動
運動を行って消費カロリーを増やすことにより、脂質異常症を含む生活習慣病全体の予防や改善に役立ちます。
特に、適度な有酸素運動はHDLコレステロールの上昇、総コレステロール、LDLコレステロール、トリグリセライドの改善が期待できることが報告されています。
■運動療法の指針(動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版)
- 有酸素運動を中心に実施する
(ウォーキング、速歩き、水泳、エアロビクス、サイクリング、ベンチステップ運動など) - 強度は楽~ややきつい程度以上を目標にする
- 毎日合計30分以上、週3日以上を目標に実施する
- 運動療法以外の時間もこまめに歩くなどできるだけ座ったままの生活を避ける
いわゆるスポーツを行う時間をとるのが難しい場合には、生活するうえで行う動作(生活活動)を増やすのも方法のひとつです。
■意識して増やしたい生活動作の例
- 通勤、買い物のための歩行
- 階段の上り下り
- 掃除、物を運ぶなどの作業
- 子どもと遊ぶ
このような動作を行う時間を増やすだけでも、消費カロリーの増加に有効ですので、無理のない内容から取り入れてみてくださいね。
禁煙
脂質異常症の改善、および動脈硬化性疾患の予防のために禁煙に取り組みましょう。
タバコは動脈硬化を進行させる原因の一つであり、血中脂質(LDLコレステロール)の数値上昇の要因のひとつでもあります。
そのほか、呼吸器系の疾患のリスクも高めるため、健康維持の観点では禁煙が望ましいでしょう。
禁煙外来や禁煙補助薬などを活用しつつ、禁煙に取り組みましょう。
まとめ
脂質異常症は食事を中心とした生活習慣が深く関係している病気です。
脂質異常症の種類によって細かい内容は異なるものの、肥満解消のためのカロリー管理のほか、食事内容の見直しが重要なポイントです。
脂質異常症において「絶対に食べてはいけないもの」はありませんが、以下のような食品は摂りすぎないよう注意が必要です。
- 高カロリーな食べ物
- 飽和脂肪酸の多い食べ物
- コレステロールの多い食べ物
- 糖質の多い食べ物
- アルコールを含む酒類
- トランス脂肪酸の多い食べ物
また、脂質異常症で積極的にとりたい食品もありますが、カロリーの過剰を避けるため、上記の「避けたい食べ物」と置き換える形で取り入れるのが基本です。
また、食事以外にも、運動や喫煙といった生活習慣の見直しも大きな意味を持ちます。
将来にわたって健康を維持するために、できるところから生活改善に取り組めるようにしたいですね。
参考文献
日本動脈硬化学会:「動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版」
厚生労働省:「日本人の食事摂取基準(2020年版)策定検討会」 報告書
文部科学省:「食品成分データベース:日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
株式会社はくばく:「もち麦ごはん無菌パック 150g×6パック」
記事監修

院長 内田 智之
- 日暮里・三河島内科クリニック 院長
- 日本内科学会総合内科専門医
- 日本血液学会血液専門医
- 日本血液学会血液指導医
- ICLSディレクター
- がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修修了
- 難病指定医

管理栄養士 平井 しおり
2013年に管理栄養士資格取得後、保育施設に勤務、栄養相談などに従事。
現在は、栄養とダイエットに関する科学的根拠に基づいた情報を発信しています。








